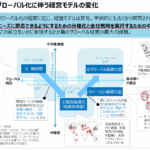キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
前回に続き、文化芸術立国についてお話します。世界各国は、近年文化芸術が有する創造性を社会の活性化に生かし、また、文化芸術を発信することによって、国の魅力を高めようとする戦略が見られます。文化庁においても「クール・ジャパン」とも称される現代の日本の文化のみならず、古くからの優れた伝統文化と併せて魅力ある日本の姿を発信することにより、世界における日本文化への理解を深めるための施策を推進しています
●文化的景観
山間に広がる棚田、野焼きにより維持される牧野、防風林が廻らされる集落等、地域における人々の生活又は生業と当該地域の風土により形成された景観地で、国民の生活や生業を理解するために欠くことのできないものを「文化的景観」と呼んでいます。都道府県又は市町村が定めた文化的景観のうち、その申出に基づき、特に重要なものを文部科学大臣は「重要文化的景観」に選定します。申出に当たり、地方公共団体は、当該文化的景観が景観法に規定される景観計画区域又は景観地区に含まれていること、自然・緑地・農地等を保全する法律に基づく条例で保存の措置が講じられていること、文化的景観保存活用計画が策定されていること等の要件を満たす必要があります。文化庁では、地方公共団体が行う文化的景観の保存調査や保存活用計画の策定、重要文化的景観の整備、勉強会や ワークショップ等の普及啓発事業等に補助を行っています。
●伝統的建造物群
周囲の環境と一体を成して歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値が高いものを「伝統的建造物群」と呼んでおり、城下町や宿場町、門前町、農山村集落などが これに当たります。伝統的建造物群を有する市町村は、伝統的建造物群やこれと一体を成して価値を形成している環境を保存するために「伝統的建造物群保存地区」を定め、伝統的建造物の現状変更の規制等を行い、歴史的集落や町並みの保存と活用を図っています。文化庁では、伝統的建造物群保存地区のうち、市町村の申出に基づき、我が国にとってその価値が特に高いものを「重要伝統的建造物群保存地区」に選定しています。
「伝統的建造物群」を持つ市町村が行う伝統的建造物群 の保存状況等の調査や、重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物の修理、伝統的建造物以外の建築物等の修景、伝統的建造物群と一体を成して価値を形成している環境の復旧、防災計画を策定するための経費、防災のための 施設・設備の整備、建造物や土地の公有化等の事業を補助しています。
●文化財の保存技術
我が国固有の文化によって生み出され、現在まで保存・継承されてきた文化財を確実に後世へ伝えていくために欠 くことのできない文化財の修理技術・技能やこれらに用いられる材料・道具の製作技術等を「文化財の保存技術」と 呼んでいます。文化財の保存技術のうち保存の措置を講ずる必要があるものを「選定保存技術」に選定するとともに、その技術を正しく体得している者を「保持者」として、技術の保存のための事業を行う団体を「保存団体」と して、それぞれ認定し、保護を図っています。
“●世界文化遺産
世界遺産条約(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)は、顕著な普遍的価値を持つ文化遺産・自然遺産を、人類全体のための世界の遺産として損傷・破壊等の脅威から保護することを目的として、昭和47年に国際連合教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ)総会で採択され、我が国は平成4年に条約を締結しました。令和6年3月末現在の締約国数は195か国になっています。毎年1回開催される世界遺産委員会では、締約国からの推薦や諮問機関の評価等に基づいて審議が行われ、顕著な普遍的価値を持つと認められる文化遺産・自然遺産が世界遺産一覧表に記載されます。令和6年3月末現在で1,199件の遺産(文化遺産933件、自然遺産227件、複合遺産 39件)が記載されています。3年7月に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」と「北海道・北東北の縄文遺跡群」が記載され、我が国の世界遺産一覧表記載物件は 文化遺産20件、自然遺産5件となっています。令和5年1月に、「佐渡島の金山」の推薦書正式版をユネスコに提出したところであり、登録に向け、引き続き取り組んでいきます。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書”
●無形文化遺産の保護に関する取組
生活様式の変化など社会の変容に伴って、多くの無形文化遺産が衰退や消滅の危機にさらされる中、平成15年のユネスコ総会において、無形文化遺産の保護に関する条約が採択され、18年4月に発効しました。我が国は、16年に3番目の締約国となりました。令和6年3月末現在、この条約には183か国が加盟しています。この条約では、無形文化遺産を保護することを目的として、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表の作成、無形文化遺産の保護のための国際的な 長崎県・熊本県 大阪府 鹿児島県・沖縄県 北海道・青森県・岩手県・秋田県 平成12年 文化 平成16年 文化 平成17年 自然 平成19年 文化 平成23年 自然 平成23年 文化 平成25年 文化 平成26年 文化 平成27年 文化 平成28年 文化 平成29年 文化 平成30年 文化 令和元年 文化 令和3年 自然 令和3年 文化 協力及び援助体制の確立、締約国が取るべき必要な措置等 について規定されています。 令和4年11月、「風流踊」が無形文化遺産代表一覧表に 記載され、現在、我が国からの代表一覧表記載件数は22 件となっています。 現在、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表への新規提案と して「伝統的酒造り」及び「書道」を、拡張提案として 「和紙:日本の手漉和紙技術」、「山・鉾・屋台行事」、「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」 を提案しています。
◆文化資源を活用した賦課かk値の創出
●インバウンドのための環境
平成28年に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」において、「文化財の観光資源としての開花」が掲げられました。令和5年3月に閣議決定された「観光立国推進基本計画」をはじめとする計画等においても、文化資源の観光資源としての魅力の向上等が掲げられており、そうした政府方針を踏まえ、文化庁では文化資源の磨き上げや高付加価値化等、インバウンドにとって文化資源がより魅力的なものとなるような取組への支援を行っています。
“●文化資源を活用した経済活性化の促進
平成31年1月に、国際観光旅客税が創設され、観光先進 国実現に向けた観光基盤の拡充・強化が推進されています。 文化庁では、文化財をはじめとした我が国固有の文化資源についても、国内外問わず多くの人々にその歴史的価値・魅力を発信するため、新たな付加価値を付け、より魅 力的なものとなるよう磨き上げる取組を支援しています。 具体的には、2025年大阪・関西万博に向けて、日本各地の最高峰の文化資源を更に磨き上げる「日本博2.0」や、 実際に文化財を訪れることで生きた歴史の体感・体験を通 じて文化財の理解を促進する取組を支援する生きた歴史体感プログラム(Living History)事業等によって、観光イ ンバウンドに資するコンテンツの創出を進めるとともに、日本文化の魅力を効果的にオンライン発信することで、観光振興・地域経済の活性化の好循環を促進していきます。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書”
◆文化観光の推進
●文化観光推進法に基づく文化観光拠点の整備
文化の振興を起点として、観光の振興及び地域の活性化の好循環を創出するためには、地域において文化の理解を深めることができる機会を拡大し、これにより国内外から の観光旅客の来訪を促進していくことが重要です。 こうした観点から、博物館等の文化施設を拠点として、地域における文化観光を推進するため、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法 律」(いわゆる「文化観光推進法」)に基づき、令和5年度 までに、51件の拠点計画及び地域計画を認定しています。 これらの計画に基づく文化資源の磨き上げ等の取組について、「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業」等により支援しました。
“●日本遺産の魅力発信
地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを日本遺産として認定する仕組みを平成 27年度に創設し、これまでに104件を認定しました。認定地域に対しては、①コンテンツ制作やガイド育成等 の情報発信・人材育成、②ストーリーの普及啓発、③調査 研究、④説明板の設置等の公開活用のための整備に対して必要な財政支援を行い、地域活性化を図っています。また、29年度に認定された17地域に対して総括評価・継続 審査を行うとともに、他の地域のモデルとなる地域として 重点支援地域を選定する等、日本遺産のブランド力の維持・強化を図りました。 令和5年11月には、東京都八王子市で各認定地域が一堂に会した「日本遺産フェスティバル㏌桑都・八王子」を開催し、ブース出展等により地域の魅力発信を行いまし た。また、日本遺産の認知度の向上等を図るため、日本遺 産の日である2月13日を記念して、シンポジウムを開催 しました。加えて、有識者委員会において取りまとめられ た「令和3年度の総括評価・継続審査を踏まえた地域活性 化計画等の改善について」(3年12月)に基づき、日本遺産ストーリーを中心とした地域の活性化・観光の振興を図 るため、重点支援地域において今後の日本遺産事業のモデルを構築するなど、日本遺産全体のブランド力向上に取り 組んでいるところです。 今後とも、これらの取組を通じて、日本遺産を活用した 地域の活性化や、日本文化の国内外への戦略的な発信に積 極的に取り組んでいきます。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書”
(つづく)Y.H