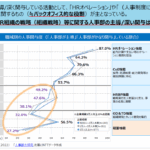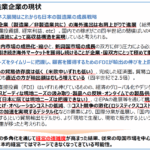キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
世界各国は、近年文化芸術が有する創造性を社会の活性化に生かし、また、文化芸術を発信することによって、国の魅力を高めようとする戦略が見られます。文化庁においても「クール・ジャパン」とも称される現代の日本の文化のみならず、古くからの優れた伝統文化と併せて魅力ある日本の姿を発信することにより、世界における日本文化への理解を深めるための施策を推進しています。今回は文化芸術立国についてお話します。
●文化芸術推進基本計画
政府は、文化芸術基本法に基づき、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術推進基本計画を策定しています。 第1期計画期間中の成果と課題を踏まえ、令和5年3月に、5年度から9年度までの5年間の文化芸術政策の基本的な方向性を定めた文化芸術推進基本計画(第2期)を閣議決定しました。本計画では、5年間で取り組むべき重点取組として、以下の七つを掲げています。 ①ポストコロナの創造的な文化芸術活動の推進 ②文化資源の保存と活用の一層の促進 ③文化芸術を通じた次代を担う子供たちの育成 ④多様性を尊重した文化芸術の振興 ⑤文化芸術のグローバル展開の加速 ⑥文化芸術を通じた地方創生の推進 ⑦デジタル技術を活用した文化芸術活動の推進 また、これに加えて、計画期間中に効果的かつ着実に文化芸術政策を推進するための16の施策群を整理し、具体的な取組を推進していくこととしています。 引き続き、文化庁が中核となり、関係府省庁をはじめとする各関係機関との連携及び協働を図りながら、本計画に基づき文化芸術施策を総合的、一体的かつ効果的に進めていきます。
●文化庁予算
令和5年度文化庁予算においては、「文化芸術のグローバル展開、DXの推進、活動基盤の強化」、「『文化財の匠プロジェクト』等の推進・充実による文化資源の持続可能な活用の促進」、「文化振興を支える拠点等の整備・充実」 など、対前年度比1億円増の1,077億円を計上しています。このほか国際観光旅客税財源を活用し、「日本博」を契機とした観光コンテンツの拡充、生きた歴史体感プログラム(Living History)事業などを通じて、文化資源を活用したインバウンドのための環境整備を推進 しています。 加えて、令和5年度補正予算として、303億円を計上しており、文化財の強靱化(保存修理、防火・耐震対策等)、国立文化施設の整備などを盛り込んでいます。これらに加 え、次代を担うクリエイター・アーティスト等を育成するとともに、その活躍・発信の場でもある文化施設の次世代 型の機能強化を、基金を活用して弾力的かつ複数年度にわたって支援するクリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援(5年の基金の3年分)のための予算を計上しています。
◆文化財の保存と継承
●文化財保護を巡る近年の動向
文化財は、我が国の歴史や文化の理解のため欠くことのできない貴重な国民的財産です。また、確実に次世代に継承していくことにより、将来の地域づくりの核ともなります。このため、文化庁では、文化財保護法等に基づき、多種多様な文化財の保存・活用のための施策を講じています。
文化財の保存技術・修理人材や用具・原材料の確保及支援の在り方、持続可能な文化財保存の在り方については、文化審議会文化財分科会の下の企画調査会において、「持続可能な文化財の保存と活用のための方策について (第二次答申)」(令和4年12月16日文化審議会文化財分科会)が取りまとめられました。また、埋蔵文化財をめぐる様々な課題については「これからの埋蔵文化財保護の在 り方について(第一次報告書)」(4年7月22日文化審議会文化財分科会)が取りまとめられ、これに基づき文部科学省において、史跡相当の埋蔵文化財のリスト化等を進めています。
令和4年12月には、上記の答申を踏まえ、文化財の持続可能な保存・継承体制の構築を図るための5か年計画である「文化財の匠プロジェクト」を改正し、文化財修理に 不可欠な原材料のリスト化・支援充実、中堅・若手技術者等を対象とした表彰制度の創設、国指定文化財の長期的な 修理需要予測調査などを新たに位置づけました。 本プロジェクトでは、引き続き、文化財の保存・継承の ための用具・原材料の確保、文化財保存技術に係る人材育 成と修理等の拠点整備、文化財を適正な修理周期で修理するための事業規模の確保等の取組を推進します。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書
●地域における文化財の保存・活用
平成30年の文化財保護法の改正により、文化財をまちづくりに生かしつつ、地域社会総がかりでその継承に取り組んでいくため、都道府県における文化財保存活用大綱 (以下「大綱」という。)と、市町村における文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の制度が規定されました。大綱は、域内の文化財の保存・活用に係る基本的な方針、広域区域ごとの取組、災害発生時の対応等を記載した文化財の保存・活用に関する総合的な施策を盛り込むものであり、令和6年3月末現在、44道府県で作成さ れています。市町村の地域計画は、できる限り域内の文化財を網羅的に把握した上で、域内の文化財の保存及び活用に関する基本的な方針、保存及び活用のために市町村が講ずる措置の内容等を記載するものであり、同年3月末現在、139市町が作成した地域計画が国の認定を受けていま す。作成した地域計画が国の認定を受けた場合、国に対して登録文化財とすべき物件を提案できる特例があります。 また、国指定文化財の現状変更の許可等、文化庁長官の権 限である一部の事務について、現状移譲されている都道府県・市のみならず、認定市町村でも特例的に自ら事務を実施できることとしています。今後、この大綱及び地域計画 の作成は多くの地方公共団体で進んでいくことが見込まれており、4年4月から施行されている地方公共団体による 登録制度の取組と併せて、各地域において、貴重な文化財 を確実に把握し、地域において守り育てる取組が進むことが期待されます。
このような地域社会総がかりでの文化財の保存・活用の取組を促進するため、「地域文化財総合活用推進事業(地域のシンボル整備等)」を設け、地域計画等に基づき地域 の核(シンボル)となっている国登録文化財を戦略的に活用するための機能維持や、保存・活用を行う団体の取組等を支援する地方公共団体を後押しすることとしています (令和5年度採択実績:15件)。
また、地域の多様で豊かな文化遺産を継承するため、 「地域文化財総合活用推進事業(地域文化遺産・地域計画等)」では、文化遺産を活用した普及啓発等の取組を支援 しています。さらに「地域文化財総合活用推進事業(地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業)」では、地域の伝統 行事や民俗芸能等の用具修理や後継者養成等の取組を支援しています。
●文化財の指定をはじめとする保存・継承のため の取組
文化財を保存・継承するため、文化庁では、文化財保護法に基づき、文化財のうち重要なものを指定・選定・登録 し、現状変更や輸出等について一定の制限を課す一方、有形の文化財については保存修理、防災、買上げ等を、また、無形の文化財については伝承者養成、記録作成等に対して補助を行うことによって文化財の保存を図っています。 また、地域の文化財を一体的に活用する取組として、文化財の公開施設の整備に対して補助を行ったり、展覧会等による文化財の鑑賞機会の拡大を図るなどの支援も行ったりしています。
●有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産や考古資料、歴史資料で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して 「有形文化財」と呼んでいます。このうち、「建造物」以外 のものを「美術工芸品」と呼んでいます。有形文化財のう ち重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに、重要文化財のうち世界文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して重点的に保護しています。 また、近年の国土開発や生活様式の変化等によって、消滅の危機にある近代等の有形文化財を登録という緩やかな手法で保護しています。
有形文化財は、主として木、紙、漆、絹等の天然素材に由来する材料で作られているものが多く、その保存・管理 には適切な周期での修理が必要であるとともに防災対策が欠かせません。そのため、修理等に要する費用や、建造物 については地震や火災等の被害から建造物を守るための工事や必要な設備の設置、危険木対策等の環境保全事業に対する補助を実施しています。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書
●無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いものを「無形文化 財」と呼んでいます。無形文化財は、人間の「わざ」そのものであり、具体的にはその「わざ」を体現・体得した個人又は団体によって表現されます。
無形文化財のうち重要なものを「重要無形文化財」に指定し、同時に、これらの「わざ」を高度に体現・体得して いる者又は団体を「保持者」又は「保持団体」として認定 しています。保持者の認定には、重要無形文化財である芸能又は工芸技術を高度に体現・体得している者を認定する「各個認定」(この保持者がいわゆる「人間国宝」)と、二人以上の者が一体となって舞台を構成している芸能の場合は、その「わざ」を高度に体現している者が構成している団体の構成員を認定する「総合認定」があります。また、「保持団体認定」は、重要無形文化財の性格上個人的特色が薄く、かつ、その「わざ」を保持する者が多数いる場合、これらの者が主な構成員となっている 団体を認定するものです。 重要無形文化財の各個認定の保持者に対し、「わざ」の錬磨向上と伝承者の養成のための特別助成金を交付するとともに、重要無形文化財の総合認定保持者が構成する団体や保 持団体、地方公共団体等が行う伝承者養成事業、公開事業等を補助しています。また、我が国にとって歴史上、芸術上 価値の高い重要無形文化財(工芸技術)を末永く継承し保 護していくため、保持者の作品等の無形文化財資料を購入し たり、その「わざ」を映像で記録して公開したりしています。 また、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文必要とされるものを登録無形文化財として登録しています。
(つづく)Y.H