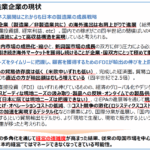Aさんの「キャリコンサルタント養成講座」受講奮闘記をお伝えします。「キャリコンサルタント実践の要領 24」に続くキャリコンサルタント養成講座8日目からの話です。
Aさんは中小企業に勤めている小学生と4歳半の子供をもつ女性ですが、ある事をきっかけに「キャリコンサルタント」という資格を知りました。厚生労働省の国家資格であること、企業の中で人間関係の相談に乗ってあげられる力を付けられることなどを知り、どこかの「キャリコンサルタント養成講座」を受けたいとNetで多くの「キャリコンサルタント養成講座」を調べました。
その結果テクノファの「キャリコンサルタント養成講座」が自分に合うのではないかと思い、3か月にわたる12日間「キャリコンサルタント養成講座」講座を受講することに決めました。決めた理由は16年の「キャリコンサルタント養成講座」の歴史と「組織と個人の共生」ということにありました。
Aさんの受講も8日目になりました。
8日目には演習の2つめのグループワークを行います。
キャリアコンサルティングは、基本は1対1で行うものですが、実務の現場では、集団に対するコンサルティングをする場面もあります。その点を踏まえた上での8日目の学習になります。講義を経てこの日は何よりもグループワークによって、集団での活動の意味を理解してもらうと共に、集団におけるコミュニケーションの大切さを体験によって得ていただきます。
まず自己紹介を兼ねて参加者全員に「好きな数字、気になる数字」を紙に書いてなぜ好きなのかを1,2分で説明するように講師から求められます。
Aさんは紙に大きく8と描き、「18高校生、28出会い、38別れ」と8のつく歳にエポックメイキングに事柄を書きました。
次のことを考えました
・ロジャーズのグループ
・Aさんの企業における体験
・AさんとBさんの簡単な説明の理解程度の確認ワーク
ー子供のころ好きだった科目
-大切にしていること
-失恋した友達に一言
【9日目 キャリアコンサルティング演習 つづき】
いよいよ9日目はカウンセリング実習です。とはいえ、いきなり実習といっても厳しいものがありますからその前にしっかり講義の時間をとっています。
第一のテーマは「傾聴」です。傾聴に関する世の中の誤解をまずはバッサリ。カウンセリング(コンサルティング)を多少学ぶとできるようになってくる、コミュニケーションにおける聞き手の立場として「うなづき」、「オウム返し」。これができるようになれば傾聴ができていると言えるでしょうか。
【10日目 キャリアコンサルティング演習 つづき 】
この日も実習の前に講義から入ります。コンサルティング実習の3日目(全体の9日目)までは主としてクライエント側の立場に立つことを学んできました。
問題(悩み)を解決する主体はクライエントであり、クライエントの気づき、内省を深めるためにカウンセラー(コンサルタント)の存在意義があるわけですが、それだけでは不十分です。ではそのために誰が何をする必要があるのでしょうか。
それはカウンセラー(コンサルタント)がクライエントの状況をアセスメントして問題を見きわめ方向づける、ことなのです。ある意味それはキャリアアドバイスです。世の中ではキャリアコンサルティングと言えばこのキャリアアドバイスと同義のようにとらえられる部分がありますが、私たちはそれでは全く不十分と考えて講座をずっと運営してきています。キャリアコンサルティング技能士試験も2級、1級とありますが、単にキャリアドバイス的な対応力しかない方は残念ながら合格レベルとは言えません。だからこそ私たちの講座ではまずクライエント側に焦点をあて、その上でキャリコンサルタント側の立場の勉強をそれに加えていきます。ここは他の講座との大きな違いと思っています。他の講座ではキャリコンサルタント側から入り、クライエント側の部分への理解を深める方式をとっているところは大半ではないかと思っています。どちらを主として考えるかの違いでしょう。私たちの講座は、クライエント側の悩みを深く理解することに重点を置いています。だからこそキャリコンサルタントはまずは自分自身を深く理解していないといけない、という立場をとっています。だからこそコース前半でCDW(キャリア開発ワークショップ)を入れているわけです。
その上で、クライエント本人の悩みとは何か、ということをより深く考えていきます。それはクライエント自身の問題と、クライエントがクライエントと関わる外部との間の悩み、葛藤の問題なのか、という違いも理解しておく必要があります。
ただし、実際のキャリアカウンセリング(キャリアコンサルティング)の場面ではクライエント自身からそのあたりの情報開示が十分になされるとは限りません。よってキャリコンサルタント側では、そのあたりの想定をしたうえで、聞き出していく(理解していく)ことが必要不可欠です。まずはそのことを知識ベースで理解していただきます。ただし、それはまだ入り口。頭でわかってもできるようになるには当然訓練が必要になります。その訓練をじっくり時間をかけて行っていく。それが10日目の主題となります。
前日の9日目と共にこの10日目のトレーニングは受講される皆様にとって非常に刺激に満ちた時間になると思っています。自らの力量がまだまだ開発余地が大きいと共に気になること、質問したいことが山ほど出てくる状況になります。CC協議会 キャリアコンサルタント試験(国家資格)
(つづく)T.A