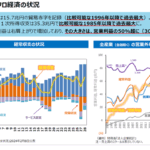このコーナーは、テクノファキャリアコンサルタント養成講座を卒業され、現在日本全国各地で活躍しているキャリアコンサルタントの方からの近況や情報などを発信しています。今回はS.Sさんからの発信です。
「生涯発達※から捉える”人生の午後”」
一昨年前、フェイスブック上で高校時代の同級生と再会した。彼は、大学を卒業した後に某一流企業に就職が決まり、これまで誰もが羨む順風満帆な人生を送ってきた。
※生涯発達
生涯発達は、個人が生まれてから死ぬまでの間に経験する変化や成長を指します。バルテスはこの概念を「人の誕生から死に至るまでの生涯過程における個人内の変化と安定性・連続性を記述・説明する学問」と定義しています。これは、発達が単なる身体的成長にとどまらず、心理的および社会的な側面も含むことを示しています。内の変化と安定性・連続性を記述・説明する学問」と定義しています。これは、発達が単なる身体的成長にとどまらず、心理的および社会的な側面も含むことを示しています。知っておきたい「生涯発達」3つの要因とバルテスの生涯発達理論とは? – ツナガレ介護福祉ケア
しかし、5年前に重い病に侵され入院して以来、彼にとって人生そのものであった仕事に就けない体となってしまった。さらに、そこに追い打ちをかけるように、一流企業の社員としての彼を選んだ妻が再起不能の夫の姿に落胆し、子どもたちを連れて去ってしまったというのである。
そんな彼が、半年ほど前からネット上に姿を現さなくなった。別の友人からの情報によると、彼は現在、極度の鬱状態に陥っており、その様子を見て放っておけないと判断した親族が、彼を実家に連れ帰ったという。
そのようなわけで、何か彼に関する情報が他にないかと、同じ地元に住む同級生たちに電話をかけてみたのだが、なんとその中の一人がこれまた鬱病で寝込んでいた。聞けば、働く意欲がまったく湧かず、35年ほど続けてきた会社を辞めて静養中だという。
じつは、かく言う僕も50歳の誕生日を迎えた翌日から、自分が自分でないような言いようのない虚しさに苛まれた体験を持っている。自殺念慮に襲われ、一時的ではあったが、まったく動くことができなくなった。幸いなことに、僕の周囲には多くのカウンセラー仲間がいてくれたし、敬愛する師に頼ることができたおかげで、今もこうやって生きていられる。
日本における自殺者の数は、年間3万人前後で推移していることが知られているが、その内訳を見れば、40代後半以降の男性が圧倒的に多い。心理学者ユングは、「人生の午後」という表現で、いわゆる「中年の危機」について語っている。
多くの男性たちは、40代後半から60歳の定年に向けて徐々に残りの人生を意識し始め、先細りの未来に不安と焦りを感じつつ、何とも言えない虚しさと虚脱感に襲われることがある。
それは、これまでひたすら頑張ってきたことが、じつは全く無駄ではなかったのか・・、いまの自分に果たしてどんな価値があるのだろうか・・、または生きていることの意味が分からなくなった・・という実存的な不安感と絶望である。
子にとっての父親、親にとっての息子、妻にとっての夫、そして仕事上における役職・・これらはどれも「役割」にすぎないのだが、そういった役割に同化していた自分に突然気づき、いったい自分が何者であるのかが分からなくなってしまうのだ。
「仕事人間」という言葉があるが、役割に埋没し、自己と役割とが不明瞭なまま区別がつかないとなれば、定年退職した翌日から自分という存在に対する疑問に悩むことになるだろう。女性の場合は、子育ての終焉によって生じる「空の巣症候群」が、身体的変化としての更年期傷害を酷く悪化させる場合が多いと言われている。
いすれにしても、これらは役割と自分について曖昧なまま、区別せずに生きてきたことに起因している。キャリアを語る場合、「私は何者か?」という命題が常につきまとう。自分にとってのアイデンティティが、名刺に書いてある役職や所属に在り、それに無自覚的に依存しているならば、定年後の私は存在の拠り所を失うことになるだろう。
ところで、「還暦」の解釈のひとつに「人生の始まり」というのがあることをご存じだろうか。つまり、「還暦までに何とか大人になろう」という意味であり、六十歳に至るまでに出会う諸々の出来事や果たすべき役割は、大人になるために必要な試練だというのである。
人は、社会人や子育てを務めた経験から多くのことを学ぶ。還暦に至るまではあくまでも修養期間でしかなく、還暦を過ぎてようやく一人前の大人として初の人生が始まるということらしい。となれば、その準備期間でしかない還暦前に絶望するなどということが、いかに不自然なことであり、未熟な証であるかをじっくりと再考してみる必要があるだろう。
生涯発達という言葉が一般化して久しいが、そもそも「第二の人生」などという捉え方自体に問題があるのかもしれないし、社会人である自分が既に完成された大人であるという認識は、誤認というより先に、単なる奢りでしかないのかもしれない。
私は何者だろう?
いま、何を為そうとしているのだろう?
「真の大人」になるために、いまいちど自分に問うてみる必要があるのではないだろうか。
(つづく)K.I