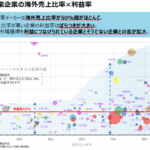キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
前回に続き、英国の労働施策の2回目です。英国は、ヨーロッパ最大の人口を誇る巨大消費市場やビジネスハブとしての優位性を持ち合わせており、英国政府も外国企業への投資を促進するための税制上のインセンティブを提供しています。例えば他の多くの国に比べて、法人税率が低く設定されていることは良く知られています。そうした中、英国に拠点を持つ日系企業は約960社、最も多く進出しているのが製造業で約330社です。
■失業保険制度等
国民保険の納付記録に基づく給付として、失業者に給付される新型求職者給付 、また長期の疾病や障害、介護などの理由で就労困難な者に対する新型雇用・支援給付があります。新型求職者給付
国民保険料を被用者として納付した期間(第1種国民保険料納付期間)が一定期間以上あり、失業者又は就労時間が週平均16時間以上でない者に給付されます。
- 新型雇用・支援給付
長期の疾病や障害、介護などの理由で就労困難な者に対して支給されます。被用者・自営業者を問わず、国民保険料を一定期間納付した者が対象です。受給開始後13週間のうちに就労能力評価の審査が行われ、障害等の程度が低い就労活動関連グループと、就労に向けてより多くの支援を必要とする支援グループに分けられます。 - 福祉給付制度
1.概要
新たな給付制度として、普遍的給付への移行が求職者や低所得者を対象に進められており、2018年12月以降は全ての新規受給申請者は原則として普遍的給付の申請をすることになりました。雇用年金省は、2024年末までに普遍的給付に統合される全ての給付制度を廃止し、普遍的給付制度へ全面的に移行することとしています。また、福祉給付制度の受給者については、一部の者を除き、給付額の上限が設定されています。
2.普遍的給付制度
求職者や低所得者を対象とした新たな給付制度で、税財源による6つの給付制度①所得調査制求職者給付、②所得調査制雇用・支援給付、③所得補助、④住宅給付22、⑤児童税額控除、⑥就労税額控除を統合したものです。
・対象
原則として18歳から年金支給開始年齢までの就労世代がいる世帯で、フルタイムの教育・訓練を受けておらず、貯蓄額が320万円以下であることが条件です。
・給付内容
普遍的給付の基礎額に加え、追加手当額が世帯ベースで毎月支給されます。また、住宅費に関する支援も受けることができます。賃金収入がある場合、賃金収入額の55%が支給停止となります。扶養する子がいるか障害等を持つ者と同居している受給者の場合、賃金収入が一定の額(住宅費支援を受けている場合は月68,800円、受けていない場合は月114,600円)までは支給停止の対象外とされています。普遍的給付の受給者が、ジョブセンター・プラスから求められる求職活動を拒否した場合には、給付の支給停止等の制裁措置が課されます。
■普遍的給付に統合される予定の給付
・児童税額控除(Child Tax Credit)
原則として、16歳未満の子(一定の訓練または教育を受けている子の場合20歳未満)がいる低所得世帯に適用される。控除額が税額を上回る場合、つまり税額から税額控除を差し引くとマイナスの額が算出される場合には、そのマイナス分について税の還付(実際には給付)を行う。世帯収入が年17,005ポンド(就労税額控除も受ける場合は年6,770ポンド)を超えると、超過1ポンドにつき児童税額控除(就労税額控除も受けている場合は、児童税額控除と就労税額控除の合計額)が41ペンス減額される。・就労税額控除
就労税額控除は25歳以上(子がいる場合・障害を持っている場合には16歳以上)で、原則週16時間以上就労している低所得世帯に適用される。普遍的給付を受給している場合には適用されない。世帯収入が年6,770ポンドを超えると、超過1ポンドにつき就労税額控除(児童税額控除も受けている場合、児童税額控除と就労税額控除の合計額)が41ペンス減額される。(出典) 厚生労働省 2022年 海外情勢報告
- 福祉給付に関する上限設定
就労を促進し、職に就いていない者に対する福祉給付を抑制するために導入されています。16歳~64歳の就労世代を含む世帯(パートナー及び一緒に住み扶養している子を含む)者に対し、普遍的給付、新型求職者給付、新型雇用・支援給付、児童手当、出産手当などの調整対象となります、給付26の合計額に対して給付できる額の上限が設定されています。ただし、以下のいずれかに該当する場合には上限は適用されません。
・労税額控除の対象者がいる世帯
・本人及び(パートナーがいる場合は)パートナーが年金支給年齢を超えている世帯で普遍的給付を受けており、税・国民保険料控除後の世帯所得が月131,600円を超えている世帯
・障害者を対象とする給付の受給者がいる世帯
・介護をしていることを理由とした給付の受給者がいる世帯
■職業能力開発
●実施機関等
実施管理と予算配分については、教育省教育・技能助成局及び地方自治体で行われています。職業教育訓練の実施機関である教育訓練プロバイダーとしては、継続教育カレッジのほか、民間の職業訓練プロバイダー、ボランティア団体等があります。全てを公的資金で運営する公共職業訓練施設はなく、教育訓練は政府の職業教育訓練政策に沿って教育訓練プロバイダーが教育訓練プログラムを提供し、その実績に対して公的資金が助成されています。なお、スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの職業能力開発政策についての権限は、各政府に委譲されています。
- 中等教育における職業教育
義務教育後の高等教育や養成訓練制度に代わる第三の選択肢として、2020年9月から職業教育であるTレベルが段階的に開始されています。中等教育修了一般資格を持つ16歳以上を対象とした2年間の職業教育で、座学と315時間以上の実地研修により構成されています。養成訓練と異なり、特定の職業ではなくより幅広い職業への対応を目指しています。また、中等教育修了一般資格を持っているが、Tレベルのすぐの開始は難しい者を対象として、1年間のTレベル移行プログラムの提供もされています。このほか、職業資格について、普通教育資格との同等性の実現を目指し、4種類の職業教育が学校で実施されています。
■養成訓練制度(Apprenticeships)
事業主のニーズに沿うように設計された職場実習型訓練であり、訓練参加者は国家認定資格を取得することができる。イングランドにおいては、教育省教育・技能助成局が所管している。事業主のグループが設計する養成訓練基準(Apprenticeship standards)に基づいて実施されており、実施にあたって、事業主は政府に登録した訓練提供事業者と契約するか、自ら政府に登録して訓練提供者となる。16歳以上でフルタイムの学生でないイングランドの住民が訓練を受けることができ、RQFレベル2以上の職業資格の取得を目指す。既に雇用されている労働者も訓練生になることが可能である。事業主の給与支払額の年間300万ポンド以上の部分のうち、0.5%が養成訓練負担金(Apprenticeship Levy)として徴収されている。徴収された額は各事業主の口座に付与されるとともに、口座拠出額の10%相当額が政府から口座に付与される。事業主は口座に付与されてから24ヶ月以内であれば、養成訓練の費用として、職種により定められた上限の範囲内で口座の残高から引き出すことができる。なお、口座に残高がない場合には、不足分の95%が政府から補助される。なお、他の事業者の口座に年間拠出額の25%の範囲内で移管することが可能となっている。口座から引き出せる額の上限については、訓練する職種別に1,500ポンドから27,000ポンドの30段階のいずれかの額が定められている。
これとは別に、①16歳~18歳の者を受け入れた場合、②障害などの理由により特別の支援を受けている19歳~24歳の者を受け入れた場合には、国から事業主・訓練提供者にそれぞれ1,000ポンドの補助がある。また、①2021年4月から2022年1月の間に養成訓練生を新規に受け入れた場合、事業主に対して3,000ポンド、②2020年8月から2021年3月の期間に受け入れた者については、16歳~24歳の場合2,000ポンド、25歳以上の場合1,500ポンド、が補助される時限措置が実施されていた。養成訓練は、以下の要件を満たす必要がある。
・訓練期間は1年以上で、原則として週30時間以上であること。
・雇用時間の20%以上(2022年8月以降開始分については週当たり6時間以上)がoff-JTであること。
・訓練生に一定程度の英語や数学の技能がない場合、必要な訓練を提供すること。
・開始前に訓練生と使用者の間で養成訓練契約を交わすこと。
養成訓練生には最低賃金が適用されるが、19歳未満または訓練開始後1年以内の養成訓練生についてはより低額の最低賃金が適用される。また、養成訓練生は1996年雇用権利法において「被用者」として扱われ、通常の被用者と同等の有給休暇を取得できる。実施される訓練は、その難易度に応じて4種類に分類することができる。また訓練の期間はレベル・資格等により異なるが、最長で5年である。(出典) 厚生労働省 2022年 海外情勢報告
■外国人労働者対策
EU離脱を受けて、2021年1月から新たな制度が導入されました。英国国籍またはアイルランド国籍を有していない者は、ポイントベース制度による審査を経て、一定以上のポイントを得ている者にビザが発給されることとなりました。技能労働者(介護と医療)については、ポイント制度において70点以上が必要とされています。
■雇用における平等の確保
2010年平等法により、直接的差別、関係者差別、認知差別、間接差別、嫌がらせ、第三者による嫌がらせ及び報復的取扱いについて保護されています。保護の対象となる属性は、年齢、障害、性別転換、人種、宗教または信条性、性的指向、婚姻・同性婚、妊娠・出産などです。2017年4月からは、2010年平等法に関する2017年男女間賃金格差情報規則により、250人以上の被用者がいる事業主は、男女の賃金格差について報告を毎年行うことが義務付けられています。
(つづく)M.H