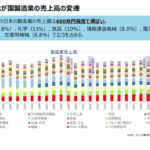キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
前回に続き、持続可能な医療・介護の実現についてお話します。少子高齢化によって、ますます労働力の減少が進んでいます。医療・介護も例外ではなく、将来的に医師や看護師、介護従事者が減っていくことは避けられません。つまり、社会と同じく需要と供給のバランスが崩れてしまう可能性があります。このバランスをどう保っていくかが、医療・介護業界の課題です。また、医療費も今後増える一方であり、税金が減ってしまえば、必然的に社会保障費の確保が難しくなってきます。
■在宅医療の推進
自宅など住み慣れた環境での療養を多くの国民が望んでおり、人生の最期まで自分らしい生活を続けることができるように支援する在宅医療提供体制の構築が望まれています。
第8次医療計画においては、適切な在宅医療の圏域を設定し、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を位置づけ、在宅医療における各職種の関わりを明確化するなど、今後見込まれる在宅医療の需要の増加に向け、地域の実情に応じた在宅医療の体制整備を進めることとしています。また、在宅医療の体制整備に対する支援としては、地域医療介護総合確保基金を活用し、在宅医療の体制構築に必要な事業に対し財政的な支援を実施しています。さらに、2015(平成27)年度から、在宅医療に関する専門知識や経験を豊富に備え、地域の人材育成事業を中心となって推進することができる講師人材の育成研修を実施しています。
■人生の最終段階における医療・ケア
人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされた上で、本人による意思決定を基本として行われるようにするため、厚生労働省では、「人生の最終段階における医療の普及・啓発の在り方に関する検討会」報告書を踏まえ、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスの概念を盛り込むとともに、11月30日を「人生会議の日」とし、普及・啓発の取組みを実施している。2017(平成29)年度からは、人生会議に関する ンポジウムの開催等を通じ、国民向けの普及・啓発を進めている。2022(令和4)年度には「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」を実施した。(出典)厚生労働省 令和6年版 厚生労働白書
■地域医療構想の策定と医療機能の分化・連携の推進
医療・介護サービスの需要の増大・多様化に対応していくためには、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制を構築する必要があります。このため、2014(平成26)年6月に成立した医療介護総合確保推進法では、病床の機能の分化・連携を進めるとともに、長期的に継続する人口構造の変化を見据えつつ、将来の医療需要に見合ったバランスのとれた医療機能の分化・連携の議論・取組みを進めるため、まずは、団塊の世代が75歳以上となり、高齢者が急増する2025(令和7)年の医療需要と病床の必要量について地域医療構想として策定し、医療計画に盛り込むこととしました。
また、2022年3月に各都道府県に対し、第8次医療計画の策定と併せて、2022年度及び2023年度に、民間医療機関等も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うことを求め、さらに、2024年3月に各都道府県に対し、2025年までの年度ごとに国・都道府県・医療機関がそれぞれ取り組む事項を明確化し、関係機関が一体となって計画的に更なる取組みを進めるという基本的な考え方を示しました。
なお、2026(令和8)年度以降の新たな地域医療構想については、現行の地域医療構想の評価・課題等を踏まえ、2040(令和22)年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含めて検討を行う必要があることから、必要な関係者が参画する検討会を新設し、検討を行うこととしています。
外来機能の明確化・連携については、都道府県において、外来機能報告により把握した結果等を踏まえ、協議を行った上で、紹介受診重点医療機関となった医療機関を都道府県ホームページ等に公表しています。
かかりつけ医機能が発揮される制度整備については、①国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるよう情報提供を強化すること、②医療機関に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認・公表し、かかりつけ医機能報告制度等の2025年4月の施行に向けて、2024年夏頃までを目途に議論の整理・取りまとめを行うこととしています。
■医療安全の確保
●医療安全支援センターにおける医療安全の確保
医療安全支援センターは都道府県、保健所設置市及び特別区に計394か所(2023(令和5)年10月1日現在)設置されており、医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者・住民に対して、医療安全に関する助言及び情報提供を行っている。医療安全支援センターの業務の質の向上のため、職員を対象とする研修や、相談事例を収集、分析するなどの取組みを支援している。 第8次医療計画では、医療安全支援センターにおける相談対応の質の向上を図るための相談職員の研修受講の推進や、医療安全推進協議会の開催等による地域の医療提供施設や医療関係団体との連携、協力体制の構築の推進等を行う。(出典)厚生労働省 令和6年版 厚生労働白書
●医療機関における安全確保の体制整備
医療事故を未然に防ぎ、安全に医療が提供される体制を確保するため、病院などに対して、医療に関する安全管理のための指針の整備や職員研修の実施などを義務づけており、個々の病院などにおける医療の安全を確保するための取組みを推進しています。
●医療事故調査制度
2015(平成27)年10月に開始した医療事故調査制度は、医療事故の再発防止につなげ、医療の安全を確保することを目的とし、2024(令和6)年3月末現在までに、医療事故報告件数3,009件、院内調査結果報告件数2,613件、医療事故調査・支援センターへの調査依頼件数246件となっており、医療事故調査・支援センターの調査は173件終了しています。
●医療に関する適切な情報提供の推進
医療に関する十分な情報をもとに、患者・国民が適切な医療を選択できるよう支援するため、①2007(平成19)年4月より開始した、都道府県が医療機関に関する情報を集約 し、わかりやすく住民に情報提供する制度(医療機能情報提供制度)について、2024 (令和6)年4月からは全国統一的なシステム(医療)による情報提供を実施するとともに、②医療広告について、2017(平成29)年の医療法改正により医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止することができるよう措置した。また、医療広告ガイドライン等を整備するほか、2017年より「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」により、医療広告の適正化を進めている。(出典)厚生労働省 令和6年版 厚生労働白書
●医療の質の向上に向けた取組み
厚生労働省では、2010(平成22)年度から「医療の質の評価・公表等推進事業」を開始しました。本事業では、患者満足度や、診療内容、診療後の患者の健康状態に関する指標等を用いて医療の質を評価・公表し、公表等に当たっての問題点を分析する取組みを助成しています。2019(令和元)年度からは、医療の質の評価・公表に積極的に取り組む病院団体等の協力を得ながら、「医療の質向上のための協議会」を立ち上げ、医療機関、病院団体等を支援する取組みを進めています
■医療医療人材の確保及び質の向上
●医療を担う人材のの確保の推進
〇医師養成数
地域の医師確保等への対応の一環として、2008(平成20)年度より、卒業後に特定の地域や診療科で従事することを条件とした地域枠等を中心に医学部入学定員を臨時的に増員してきました。全国レベルで医師数は増加してきた一方で、将来的には人口減少に伴い、医師需要が減少局面となることが見込まれており、長期的には供給が需要を上回ると考えられています。 こうした中、2026(令和8)年度以降の医学部定員については、「医師養成過程を通じ た医師の偏在対策等に関する検討会」等における議論の状況を踏まえ、検討を進めています。
〇医師の確保
必要な医師を確保するため、2018(平成30)年に成立した「医療法及び医師法の一部を改正する法律」(平成30年法律第79号)に基づき、各都道府県において、2019(令和元)年度までに、都道府県及び二次医療圏ごとの医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価した医師偏在指標を踏まえた医師の確保の方針、目標とする医師数、目標達成に向けた施策を盛り込んだ「医師確保計画」を策定し、医学部入学定員に、医師不足の地域や診療科での勤務を条件とした「地域枠」を設定 し、一定期間、医師の確保を特に図るべき区域等での勤務等を条件に返済を免除する修学資金を貸与します。また、医療機関や医師・学生等に対する必要な情報の提供や医師の派遣を行う地域医療支援セ ンターの運営 などの取組みが行われており、厚生労働省においては、地域医療介護総合確保基金等により、地域の実情に応じた都道府県の取組みへの支援を行っています。
(つづく)Y.H