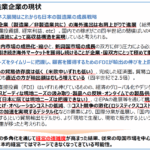◇◆◇◆ テクノファは、あなた自身が輝いて働く(生きる)ためのトレーニング・講座をご提供しています。◇◆◇◆
━ 今月の目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
——————————————————————————–
【コラム】 キャリア・カウンセラーだより”松田将矢さん”
——————————————————————————–
【トピック1】更新講習のご案内
——————————————————————————–
【トピック2】鈴木秀一さん書籍のご案内
——————————————————————————–
■□■━━【コラム】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■
キャリア・カウンセラー便り”松田将矢さん”です。
◆このコーナーは、活躍している「キャリア・カウンセラー」からの
近況や情報などを発信いたします。◆
================================================
更新講習を通じて考えた「対面コミュニケーション」の価値 松田 将矢
キャリアコンサルタント養成講座第41期生(2019年10月~12月)の松田将矢です。養成講座を卒業してから5年が過ぎ、今度は更新講習でテクノファにお世話になったことをきっかけに、本コラム執筆の機会をいただくこととなりました。
今回は現在進行形で更新講習を受講しながら私が感じている、対面コミュニケーションの価値について、お話できればと思います。
資格更新で多くの方が経験するであろう「期限が迫って慌てて計画を立てる」という状況に私も陥ってしまいました。どんな研修を組み合わせて講習時間をクリアするかあれこれ考える中で、当初は「効率優先」で費用が比較的リーズナブルなもの、自宅から参加できるオンライン実施の講習を軸に選んでいたのですが、いくつか興味のあるテーマについてはテクノファの対面講座も申し込むことにしました。
いきなり対面講習を受けるのは心理的なハードルがあり、最初はオンライン講習を受けることとし、折角なので対面なら遠くて選択肢に挙げられない実施機関のものを受講することにしました。講習を探す中で全国に実施機関が数多く存在しており、オンラインを活用することで選択肢が大きく広がることを知ることができたこと、参加メンバーが本当に様々な地域から参加しており、キャリアコンサルタントの皆さんがそれぞれの現場でキャリア支援に奮闘されていることを知ることができたことは、オンライン講習に関する個人的な収穫になったと感じています。
その後、幾つかのオンライン講座を受けた後、テクノファで対面の講座を先日受講しました。そこでは資格更新のためだけでなく自身のキャリアを改めて見つめ直す貴重な機会を提供してもらったと感じています。私は今回「シニアのライフキャリアデザイン」という講座を受講しました。
もともと、私が現在関わる会社内キャリアコンサルティングにおいて、活用が進んでいない50代以降の相談者に対して、セカンドキャリアの課題を理解した上で寄り添う方法を学ぶことが元々の目的でした。
更新講習の中で様々なグループワークを行いましたが、その中でライフキャリアレインボーを用いたワークショップがありました。養成講座以来久しぶりに真っ白なフォーマット用紙に自身が生涯において果たす様々な役割を色塗りし、過去から現在、未来へと続く自身の役割の変化を可視化しました。そのワークショップを通じて養成講座時に自身の課題として認識していた「市民」としての役割の希薄さについて、当時の記憶を久々に思い出すとともに、今もそれが変わっていないことを再認識することができました。
こうした自身の想いに気づけたのは、対面形式であったことが大きいと考えています。オンラインでは一人で考えたことを、順番にフィードバックするというプロセスに終始してしまうことが多いと感じるのですが、対面形式では自分の考えをその場で発信し、他者からリアルタイムでフィードバックをもらえることによる安心感や、こうしたプロセスがタイムラグなく続くことを通じて自分の中の気づきが導出されたと感じました。また同じ空間でのワークショップ外の何気ない会話が、相手の感情や意図をより深く理解し、本音で意見交換を行えるコミュニケーションの場づくりとして非常に有用であることを実感できたとも感じています。
こうしたオンライン/対面による伝わり方の違いはキャリアコンサルティングだけでなく、職場における上司や部下との日常的なコミュニケーション等、日常でも漠然と感じてはいたものの、キャリアコンサルタント更新講座という同じ枠の中で、自分の感じ方に違いがあることを改めて感じたことで、その思いが明確になったと感じています。キャリアコンサルタント更新講習に限らず、現在のようにオンライン、対面のハイブリッドで機会が提供される状況は大変恵まれていると感じます。
一方で自身の効率を優先した手段に偏ると、コミュニケーションの本質である相手への働きかけや相互理解を犠牲にした、形だけのコミュニケーションに陥る可能性があることを、実感をもって認識できた気がします。
「資格更新」という元々の目的から考えれば、効率優先も大事な要素であり、オンライン受講を上手に活用すべきと思いますが、キャリアコンサルタントの本質的な役割を考えるとき、相手の思いを汲み取り、信頼関係を築き上げるための「対面コミュニケーション」の価値を、身をもって感じることは大変重要だと感じています。
5年に1度、そうしたコミュニケーション手段による伝わり方の違いについて思いを至らせるという意味でも、対面講習を敢えて選び、参加者同士の交流や、講師との直接的なコミュニケーションから得られる学びの価値を実感することが必要なのではないかと今は考えています。
◆おわり◆
=======================================================
【トピック1】更新講習のご案内
================================
「例外探し」を活用したナラティブ・アプローチ
(コースID:CD19) <技能講習 9時間>
開催日:2025年5月10日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd19.html
アドラー心理学を活用した勇気づけアプローチ
~ラポール構築とクライエント理解~
(コースID:CD20) <技能講習 7時間> 開催決定しています
開催日:2025年5月17日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd20.html
「LGBTと向かい合うキャリア形成支援-入門編」
~基本的な理解と実践のための基礎スキルの習得~
(コースID:CD21) <技能講習 7時間>
開催日:2025年5月18日(日 Webセミナー
https://www.tfcc.jp/renewal/cd21.html
キャリアコンサルタントによる職場復帰支援
(コースID:CD17) <技能講習 6時間>
開催日:2025年5月24日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd17.html
ストレスコーピングを活用した面接実技演習
(コースID:CD14) <技能講習 6時間>
開催日:2025年6月7日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd14.html
アンコンシャス・バイアスを理解したクライエントサポート
(コースID:CD23) <技能講習 6時間>
開催日:2025年6月14日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd23.html
シニアのライフデザインファシリテーション
(コースID:CD18) <技能講習 7時間> 開催決定しています
開催日:2025年6月28日(土)テクノファ川崎研修センター
https://www.tfcc.jp/renewal/cd18.html
知識講習(コースID:CD10) <知識講習 8時間>
https://www.tfcc.jp/renewal/cd10.html
知識講習はオンデマンドで学ぶことができます。
===================================================
【トピック2】鈴木秀一さんの書籍のご案内
===================================================
メルマガを購読の方は奇数月にコラムを執筆されている、鈴木秀一さんの本が出版されました。
[無知の罠 叡智の扉 人生が変わる 新・子育て進化論―行動変容から意識変容へ]
が発売されました、読み応えのある1冊です、私も早々に購入しました。
皆さんもお手に取ってみて下さい。
https://www.amazon.co.jp/dp/4911133317/ref=sr_1_1?crid=GBH3HUK4GRCB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.g9kpUd-c-EyyPLsQlaOJ0eBinwIk5Cm0IIUpNcadsWrGjHj071QN20LucGBJIEps.9PSSPhSrz1bLjDEOLjFJ6Dxwx83VlMRgOrybcl-x0Dw&dib_tag=se&keywords=%E7%84%A1%E7%9F%A5%E3%81%AE%E7%BD%A0&qid=1742347293&s=books&sprefix=%E7%84%A1%E7%9F%A5%E3%81%AE%2Cstripbooks%2C158&sr=1-1&fbclid=IwY2xjawJLI7VleHRuA2FlbQIxMAABHRJEhU3nKKPQNlxdFKALU4UnSwekNglOO8s1b1ZRt4NI0MM8HRuXueI1AA_aem_y1WGQlbR2MDtkczfx8kGhA
上記からお申込みください。
——————————————————————————–
——————————————————————————–
▼編集後記▼
関東地方は桜が咲いています、雨続きでめちゃくちゃ寒いです。
桜が長持ちしてほしいなぁと思いつつ、街路樹の桜を眺めています。
私たちは季節の移り変わりをこんなにも心待ちにしているのだと改めて思います。
季節の次は自分自身も変わっていくことが求められますね、
今日より明日、ちょっとでも成長しているように変化を重ねていきたいです。
(い)