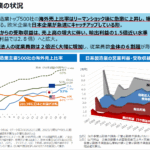キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
高等教育は、中等教育を修了した者またはそれと同等以上とみなされた者が、知識、倫理、技術などを深く学び、さらにそれらの理論や実践を身につけます。そのことを通じて、過程を終了した後に職業人となるなどして広く社会に、教育の成果を還元します。
今回は、高等教育の充実についてお話します。
◆高等教育施設の動向
●大学改革を取り巻く現状
我が国の高等教育機関への主たる進学者である18歳人口は、平成4年の約205万人をピークに令和5年には約110万人まで減少し、国立社会保障・人口問題研究所の令和5年推計では、23年には79万人に減少すると推計されています そのうえ、人口動態統計速報によれば令和5年の出生数は76万人を切り、当初の推計をはるかに上回るスピードで18歳人口が減少しています。一方、経済開発協力機構 (OECD)の調査によると、2年度の我が国の大学学士課程又は同等レベルへの進学率は52.1%であり、OECD平均と同水準です。さらに、専門学校等も含めた高等教育機関全体への進学率は76.0%であり、OECD平均の59.1%を上回っています。
◆学生に対する支援
●教育費に係る家計支出
大学生の約8割が在学する私立大学に子供二人が通っている場合の家計を例に、平均的なデータを用いて教育費負担を推計すると、勤労世帯の可処分所得のうち教育費が最大2分の1近く占めており、家庭にとって教育費の負担は大きい。学生等が経済的な理由で進学・修学を断念することがないよう、経済的支援を充実させることが重要です。
●修学支援新制度
経済状況が困難な家庭の子供ほど大学等への進学率が低いことを踏まえ、令和2年4月から、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の子供たちに対し、授業料等の減免と給付型奨学金の支給を行う高等教育の修学支援新制度を実施し、5年度は約34万人に支援を行いました。本制度は、支援を受けた学生等がしっかりと学び、社会で自立し活躍できる人材の育成を目的としています。このため、支援開始時に高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高等学校等が、レポートの提出や面談等により本人の学修意欲等を確認し、要件を満たす人全員を支援する一方、支援開始後は、学修状況に厳しい要件を課し、これに満たない場 合には支援を打ち切る仕組みとしています。また、社会で自立し活躍できるよう質の高い教育を実施する大学等を支援措置の対象とするため、大学等にも一定の要件を課しています。
●貸与型奨学金事業
令和5年度の日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金事業全体の貸与人員は約120万人、事業費総額は約 8,907億円となっています。無利子奨学金については、意欲のある学生等が経済的理由により進学を断念することがないよう、貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与を確実に実施しており、貸与人員は約50万人、事業費総額は約2,958億円となっています。
有利子奨学金は在学中には利子が課されず、卒業後にそれまでの貸与額に対して利子が課されます。このほか、家計支持者の失業や被災等によって緊急に奨学金を必要とする学生等に対応するため、貸与型奨学金の「緊急採用 (無利子)・応急採用(有利子)」の申込みを随時受け付けています。 また、令和6年度から、大学院修士段階において、在学中は授業料を徴収せず、卒業後の所得に応じて納付する授業料後払い制度を実施します。JASSOの貸与型奨学金の返還は、貸与が終了した翌月から数えて7か月目から始まります。JASSOの貸与型奨学金事業は、卒業・修了した学生等からの返還金を次の世代の学生等への原資としており、JASSOにおいては、各学校の協力を得て、学生等の返還意識を高めるとともに、返還相談体制をさらに充実するなどしています。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書
●大学院生の経済的支援の拡充
「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」(令和2 年1月23日総合科学技術・イノベーション会議)や「第 6期科学技術・イノベーション基本計画」(3年3月26日 閣議決定)における目標達成に向けて、特に博士後期課程学生の支援の充実を政府全体で進めることとしています。 文部科学省では、特別研究員事業(DC)やJASSOの貸与型奨学金事業における業績優秀者返還免除に取り組むとともに、各大学における授業料減免や学内奨学金、RA (リサーチ・アシスタント)*3制度等、多様な財源を活用し た経済的支援策の促進を行っています。 これらに加え、大学ファンドによる博士後期課程学生へ の支援開始に先駆けて令和3年度に開始した、博士後期課 程学生への経済的支援とキャリアパス整備を一体として行 う大学への支援などにより、5年度には合計で新たに約 9,800人規模の博士後期課程学生への経済的支援を実現し、引き続き支援の拡充を図っているところです。
●学生等の就職活動
文部科学省と厚生労働省は、毎年共同して大学等卒業者 の就職状況を調査しています。令和5年度の大学の学部卒業者の就職率は前年度同期比0.8ポイント上昇の98.1%と なり、調査を開始した平成8年度以降の最高値となりました。文部科学省では引き続き、大学等や関係府省とも連携し、経済団体等に対して卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすることなどの要請を行っているところです。
“●国立大学改革
国立大学は、高度な学術研究の推進、計画的な人材育成、地域活性化への貢献や高等教育の機会均等の確保といった重要な役割を果たしています。 平成16年の国立大学の法人化以降、国立大学においては、それぞれの特色や長所を生かした自主的・自律的な機能強化に向けた取組が進められてきました。昨今の急激な社会経済状況の変化の中で、国立大学に対しては、産業競争力強化・イノベーション創出の拠点としての役割や、地方創生の中核的拠点としての機能の発揮など、我が国の成長と発展への積極的な貢献をしてほしいという社会の大きな期待が寄せられています。こうした国立大学の継続的・安定的な教育研究活動を支える基盤的経費である国立大学法人運営費交付金は、令和5年度予算において1兆784億円を計上しています。4年度に国立大学の第4期中期目標期間が始まるにあたり、配分に係る見直しを行い、各大学のミッションを実現・加速化するための支援を充実するとともに、改革インセンティブの一層の向上を図っています。また、令和2年2月から「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」において、国立大学法人のガバナン スの在り方や経営の自由度を高めるための規制緩和等につ いて議論が行われ、同年12月に最終とりまとめを公表しました。この最終とりまとめ等を踏まえ、文部科学省では 3年5月に学長選考会議の権限の追加や監事の体制の強化、国立大学法人による出資の範囲の拡大等を内容とする 国立大学法人法の一部改正を行いました。 さらに、第4期中期目標期間(令和4年から9年度)に向け、中期目標大綱の提示や評価指標の義務化等の新たな 仕組みを導入したところです。 これに加え、人事給与マネジメント改革として、若手教 員の活躍機会を創出し、教員の挑戦意欲を向上できるよ う、年俸制の完全導入をはじめ、厳格な業績評価やクロス アポイントメント制度等、様々な取組を総合的に促進していきます。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書”
◆大学入学者選抜の改善
●大学入学者選抜改革
大学入学者選抜は、高等学校教育と大学教育とを接続し、双方の改革の実効性を高める上で重要な役割を果たすものです。大学入学者選抜の改革においては、受験生の知識・技能だけではなく、思考力・判断力・表現力等や、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を評価していくことを目指しており、「大学入学共通テスト」と「個別選抜」を通じて、受験生のこれら学力の3要素を適切に把 握し、大学入学段階で入学者に求める力を、多面的・総合 的に評価する入学者選抜に転換することとしています。
“●大学入学共通テスト
大学入試センター試験に代わり、令和3年1月から大学 入学共通テストを実施し、6年1月の試験では、約46万人が受験しました。共通テストは、思考力・判断力・表現 力等を発揮して解くことが求められる問題を重視するとともに、授業において生徒が学習する場面や、社会生活や日常生活の中から課題を発見し解決方法を構想する場面、資料やデータ等を基に考察する場面、学習の過程を意識した場面の設定を重視した問題を出題することとしています。 さらに試験実施後には、自己点検評価や第三者評価を実施 し、その結果を踏まえ、更なる良問の作成に努めることと しています。また、令和4年度の試験で生じた刺傷事件や不正行為等を受け、大学入学者選抜協議会において、安全対策や不正 対策について整理が行われ、5年度と同様「令和6年度大学入学者選抜実施要項」において、対応の徹底を要請しました。その後も、不正行為の防止にあたり、受験生や関係者への注意喚起を行い、各大学において実施要項等に基づき試験が実施されました。(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学白書”
●地域に開かれた高等教育
地方公共団体、地元産業界、他の高等教育機関等を巻き込み、 地域のニーズを的確に捉えつつ、地方創生に資する魅力ある地方大学の実現のために、令和3年度に、特例的な定員 増を認める仕組みを創設しました。さらに、中央教育審議 会大学分科会において地方創生に資する魅力ある地方大学を実現するための議論が重ねられ、同年12月に「これからの時代の地域における大学の在り方について―地方の活 性化と地域の中核となる大学の実現―」が取りまとめられました。引き続き、関係省庁とも連携の上、地域にとってかけがえのない大学の実現に向けた取組を進めていきます。
(つづく)Y.H