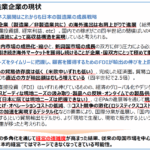キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
人手不足は、日本社会における深刻な問題です。高齢化や少子化など社会構造の変化により、労働力の供給が減少しており、特に医療・介護業界やIT業界、物流業界などで人手不足が深刻化しています。また働き方の多様性や需要の高まりも人手不足の要因となっています。
今回は、人手不足への対応についてお話します。
■2010年代以降の人手不足は「長期かつ粘着的」
●ハローワークにおける求人の充足率をみても、おおむね労働力需給が引き締まっている時期に低下する傾向があるものの、特に 2010年代以降では長期にわたり低下している。特に、フルタイム求人においては、2009年をピークに、その後大きく低下しており、2023年には10%程度と、この半世紀で最低水準となっている。同じく人手不足であった1990年代と比較しても、短期での離職を防ぎ、欠員の総数は減らす一方、生じている欠員の求人を充足することが困難となっていることがうかがえる。特に、フルタイム労働者は、企業の中核的人材であることが想定され、採用活動も長期化しやすい可能性があることから、企業は欠員率以上に人手不足を強く実感しているものと考えられる。 こうしてみると、2010年代から現在まで続く人手不足は、「短期かつ流動的」であった過去の局面と比べて「長期かつ粘着的」であり、欠員率が示す程度以上に深刻となっている可能性がある。
■今後も続く高齢化により人手不足が進む可能性がある中、生産性や労働参加率の向上が必要。
●現在、我が国は急速な人口の減少に直面しており、総人口は、2050年代に1億人を割り込むとされている。これは、これから約30年の間に、我が国の人口の約5分の1が失われることを意味している。こうした中、我が国の65歳以上人口と高齢化率の見通しについてみると、65歳以上の高齢者は、2023~2040年までで300万人程度増加することが想定され、65歳以上の高齢者が人口に占める割合は、2040年には35%弱まで 上昇するものと見込まれている。 こうした高齢化の進展は人手不足にどのような影響を及ぼすだろうか。2023年時点から消費水準や高齢者の労働参加率が現在と変わらないものと仮定する。そうすると消費水準については、景気、物価、賃金等による影響を受けるため、相当の幅をもってみる必要があるが、これによると、総消費の低下は高齢化による社会全体の労働力供給の低下よりも低下幅は小さくなっている。これは、高齢者でも生活には一定の消費が伴う一方で、高齢者の引退は、時期やどのような形かなどの差はあるものの、全ての人の職業人生において不可避的に生じるものであるためと考えられる。そのため、仮に今後、労働生産性の水準に現在から変化がないとすれば、更に人手不足に拍車がかかることが想定される。ただし、現在、時間当たりの労働生産性は2013~2022年において年平均 1.3%上昇しており、また、同期間の65歳以上の高齢者の労働参加率も20.5~25.6%まで上昇している等、ここ10年間でみても、労働力供給は増加している。この結果は、我が国の人 口が減少していく中にあって、社会の活力を維持していくためには、社会全体で労働生産性や 労働参加率の上昇に向けた取組を進めていくことが必要となることを示唆している。
(出典)厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析
■大企業への転職は活発となっている
●幅広い産業・職業で人手不足がある中で、労働移動にはどのような変化が生じているだろう か。1,000人以上規模企業からの転職について みると、同規模の企業への転職率が上昇しており、大企業間の転職は活発になっている。一方 で、100~999人や5~99人規模の中小企業への転職率は1%程度まで低下している。100~999人規模企業をみると、1,000人以上規模や100~999人規模の企業へ の転職率が2000年代と比べ上昇傾向にあり、前職以上に大きい規模の企業への転職が進んで いることが確認できる。5~99人規模企業についてみると、一貫して同 規模の企業への転職率が高いが、長期的に低下傾向にある。一方で、1,000人以上規模企業へ の転職率が上昇傾向にある。 総じてみれば、2000年代と比べ、前職以上の規模の企業への転職は活発になる一方で、規模が小さい企業への転職は低調となっており、相対的に賃金などの労働条件が良く、福利厚生なども充実している大企業への労働移動が進んでいることがうかがえる。
◆誰もが活躍できる社会の実現
■潜在労働力の状況について
●一人当たりのアウトプット(労働生産性)を上昇させることが欠かせない
我が国では、長期的な人口減少が見込まれる中で、持続的な賃上げを実現するためには、少ない人数で付加価値を得られるよう、一人当たりのアウトプットである労働生産性の上昇が欠かせない。社会全体としてのサービスを維持するためには、誰もが参加しやすい労働市場の実現等を通じて、総労働力供給を増やすことが重要である。 我が国の時間当たりの実質労働生産性は、OECD諸国37か国の中でもおおむね中位程度となっている。2013年時点で労働生産性が高い20か国(日本を含む。)をみると、うち11か国は、2013~2022年までの労働生産性の年平均成長率が我が国よりも高く、成長率の高い国と我が国の差が更に開いている。仮に労働産性が十分あがらない状況において、労働力供給の増加だけが実現すれば、賃金を据え置いまま雇用を増やすことで収益をあげることにより、結果として賃金の下押し要因となってしま う可能性がある。持続的な賃上げと人手不足への対応に同時に取り組むためには、労働生産性 の着実な上昇が不可欠である。生産性の向上に向けては、人手で行っていた作業でのロボッ ト・AI・ICT等の技術などの活用、現場の知見をいかしたデータ分析の活用による高付加 価値の商品・サービスの提供等を進めていく必要があり、こうした生産性向上への企業の取組や人材育成が欠かせない。また、厚生労働省としても、生産性向上に資する設備投資等を行 う中小企業への業務改善助成金の給付を行うとともに、人材開発支援助成金や教育訓練給付 の拡充などによるリ・スキリング支援を行っており、引き続き、生産性向上に向けた必要な支援を行っていく必要がある。
(出典)厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析
●就業希望のないい無業者は3,000万人。理由は病気・けが・高齢のためが多く、59歳以下の女性では出産・育児・介護・看護・家事のためが多い。
次に、労働力供給の増加についてみてみる。我が国において長期かつ粘着的な人手不足が生じており、広範な産業、職業、地域において労働力の供給不足が生じている。それでは我が国において労働力供給増加の余地はどれほどあるのだろうか。就業していない層を分けると、
①就業希望のない無業者
②求職活動はしていないが就業希望のある無業者、
③求職者
に分けられる。まず、最も人数の多い①の就業希望のない無業者(在学者を除く。)についてみてみる。2022年時点で約3,000万人近くが無業者であり、年齢に限らず総じて女性が多い。年齢別にみると、男女合わせて、60~69歳が440万人、70歳以上が2,100 万人と大半を占めているが、59歳以下でも350万人ほどとなっている。就業を希望しない理由としては、「病気・けが・高齢のため」が、男女ともに60~69歳の5割弱、70歳以上の8割強と最も多い。無業者が就業を希望しない理由は、病気・けがや年齢が多いが、単に高齢で あるからといって就業の希望をあきらめることとなっているのであれば、高齢化が進む我が国社会においては大きな損失である。作業内容の工夫や機器の活用を促すなど、年齢にかかわ らず働くことができる社会づくりを進めていく必要がある。 一方で59歳以下の女性の約4割に当たる約100万人が、「出産・育児・介護・看護・家事 のため」に無業かつ就業希望なしとなっているが、同年代の男性は僅かにとどまる。育児や家事、介護の負担が女性に偏っていることが、女性の就労への希望を失わせている可能性が示唆 される。育児・介護などの負担の軽減に向けた社会的支援を進めるとともに、男性が家庭内で の責任を果たせるよう、柔軟な労働時間や休暇の取得促進など職場における環境づくりも重要となる。
また、男女ともに「仕事をする自信がない」とする者が男女合わせて約70万人となっている。就労に関して自信が持てない無業者に対しては、地域若者サポートステーションにおける支援やアウトリーチ型の自立支援等も重要であろう。こうした様々な支援を着実に実施していくことで、社会全体として、就労を阻害する要因を取り除くことが重要である。
●上記②の求職活動はしていないが就業希望のある事業者は、460万人。59歳以下の女性は出産・育児・介護・看護のためが多い。
年齢別にみると、59歳以下が多く、女性は200万人近くに及ぶ。求職活動を行っていない理 由をみると、「病気・けが・高齢のため」が、高年齢層を中心に多く、男性では60万人程度、 女性では70万人程度である。「出産・育児・介護・看護のため」は59歳以下の女性が60万人程度と最も多い。また、これらに比べると数は少ないものの、「仕事を探したが見つからな かった」「希望する仕事がありそうにない」「知識・能力に自信がない」と回答した者も男女・ 年齢階級別にそれぞれ数万人程度となっている。ハローワークでのマッチングにおける丁寧な 相談支援、公的職業訓練などのリ・スキリングの支援を通じて、就業希望を求職活動につなげていくことが重要となるだろう。
(つづく) Y.H