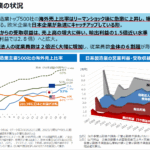キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
人手不足への対応についての最終回です。人手不足は、日本社会における深刻な問題です。高齢化や少子化など社会構造の変化により、労働力の供給が減少しており、特に医療・介護業界やIT業界、物流業界などで人手不足が深刻化しています。また働き方の多様性や需要の高まりも人手不足の要因となっています。
■正規雇用労働者は労働時間を減らしたい者が、非正規雇用労働者は労働時間を増やしたい者が多い。
●ここでは労働時間に注目してみたい。正規雇用労働者では、労働時間を「増やしたい」が約100万人、「減らしたい」が約 650万人と減少希望が多い。非正規雇用労働者では様相が異なり、労働時間を「増やしたい」 が約190万人に対し、「減らしたい」は約110万人となっている。 副業・兼業については、追加的な就業の希望の実現だけではなく、成長分野への円滑な労働移動を図る端緒としても重要である。また、個別の企業の中にも、副業・兼業 を労働者が社内では得られない経験を得ることができる成長の場として捉え、積極的に支援をしている例もみられる。厚生労働省においても、「副業・兼業の促進に関するガイドライン (令和4年7月8日改定)」を策定し、企業や労働者が、安心して副業・兼業に取り組めるよう、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示しているところである。
●総じてみると、正規雇用労働者については、引き続き、働き方改革や、仕事と家庭の両立支援などを着実に進める一方で、追加的な就業の希望には、副業・兼業への支援も含めて、心身ともに無理のない範囲で生き生きと働けるような環境づくりに取り組む必要がある。 また、労働時間の増加を希望する非正規雇用労働者には、労働時間が短時間にとどまらざるをえない障害を取り除いていく必要がある。短時間労働者が労働時間を抑制する要因の一つと しては、いわゆる「年収の壁」の存在があげられる。「年収の壁」を意識せずに働けるようにすることで、労働時間又は年収が一定の水準を超えた場合には、厚生年金保険等の被保険者となり、将来的に受け取れる年金額が増加するほか、扶養にとどまるように労働時間を短くする就業調整が行われなくなることで、人手不足の緩和にも一定の効果があるものと考えられる。 このため、パート・アルバイトで働く方の厚生年金保険や健康保険加入に併せて、手取り収入を減らさない取組として、手当等の支給や労働時間の延長を行うなどの収入を増加させる取組 を行った事業主に対し、キャリアアップ助成金として労働者一人当たり最大50万円の支援を行うとともに、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的にあがったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作る等の支援を講じているところである。引き続き、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを後押ししていくことが重要である。 (出典) 厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析
◆女性の活躍推進について
■女性の就業率は国際的にも遜色ない水準だが、パート比率が高い。
●我が国における女性の労働参加の状況について1995年と2022年とで確認してみよう。 1995年についてみると、我が国における25~54歳女性の就業率もパー ト比率のどちらもおおむね平均程度で、日本の女性の就業率は63.2%と、当時高かったノルウェー(77.4%)、デンマーク(75.9%)、フィンランド(73.5%)等の北欧と比較して10% ポイント以上低い状況であった。2022年についてみると、世界的に女性活躍が進む中で、我が国の女性の就業率は79.8%と、ノルウェー(81.9%)、デンマーク (82.4%)、フィンランド(82.1%)等の北欧とほぼ遜色ない水準まで上昇している。一方で、パート比率については、世界的な低下と対照的に我が国は30%を超える水準にまで上昇し、OECD26か国中5番目に高い国となっている。
●我が国の女性の正規雇用は年齢があがるほど比率が下がる。
年齢別に女性の正規雇用比率をみると、2023年においては全ての年齢階級で上昇している。若い世代において特にその傾向がみられるものの、年齢があがると正規雇用比率が低下する傾向が引き続き見受けられる。年齢と正規雇用比率の関係の背景には、2000年代頃までは出産等を機に退職した正規雇用の女性の多くが、復職にあたって家事・育児等への負担等から、パート・アルバイトを選ぶことも多いことが考えられる。正社員の就業継続率をみると、2000年代では就業を継続した正規雇用の女性の割合は50~60%程度と半分程度であり、多くの正規雇用で働いていた女性が就業を断念したことが確認できる。一方、2015~2019年に第1子を出生した正規雇用の女性では、80%超が出産後も就業継続し、このうち多くが育児休業を取得している。
●この30年において女性の労働参加は顕著に進んだが、パートタイム等の非正規雇用に偏る傾向が依然としてみられる。この背景には、2000年代頃までは出産を機に多くの女性が正規雇用としての就業を断念していたこと、また、女性が再就職する場合には、家事・育児の負担等も踏まえて非正規雇用を選択せざるをえない環境にあることが考えられる。非正規雇用と しての就業は、働く時間を柔軟に選択できる等のメリットがある反面、正規雇用との職責等の違いにより賃金が低く、教育訓練を受ける機会が乏しい等のデメリットもある。さらに、正規雇用から一度退職してしまうと、いわゆる日本型雇用慣行のある中で、時間外労働を伴うことがある正規雇用として再就職するのは容易ではない可能性も示唆される。就業の「量」の面では、女性の就業率は着実に上昇してきたが、「質」の面では、パートタイム比率が引き続き高い状況にある。希望すれば正規雇用として就業できる環境整備が重要である。 引き続き、育児休業制度等の充実により、希望すれば正規雇用としての就業を継続できる環境を整備するとともに、キャリアの一時的な中断が女性の職業人生の選択肢を狭めないよう、正規雇用として復帰できる環境整備やハローワークでのマッチング支援を充実していく必要が ある。あわせて、マッチング機能を強化するため、労働市場の見える化を図るとともに、有期雇用労働者等の正社員転換を促すため、キャリアアップ助成金等を通じた支援を着実に講じていくことも重要である。 (出典) 厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析
◆高齢者の活躍推進について
■我が国の高齢者の就業率は既に国際的にはかなり高い水準にある
●高齢者の労働参加の現状について確認しよう。65歳以上の 高齢者の就業率について、他のOECD諸国と比較すると、我が国は韓国・アイスランドに次いで高い水準にあり、国際的にみても高齢者の就業は進んでいることが確認できる。長期的な高齢者の就業率の推移をみると、1970年代~2000年代までは低下傾向 だったが、高年齢者雇用安定法の改正による定年年齢の引上げ等もあり、2000年代後半で 反転している。2023年には、60~64歳の就業率は70%を超え、65~69歳の就業率も50%超で、この半世紀で最高水準となった。70歳以上の就業率についても、2013年の13%から 2023年には18%と、5%ポイント上昇している。(出典) 厚生労働省 令和6年版 労働経済の分析
●この20年間で、男性において顕著に生じていた60歳における「就業率の崖」をおおむね解消できたが、足下では、65歳を境に新たな「崖」が生じている。男女ともに健康寿命が70歳 を超えていることや、65歳を超えた高齢者の就労希望が他国と比較しても高いこと、中高年層の賃金のフラット化が進んでいること等を踏まえれば、65歳を超えても意欲のある高齢者が、能力を十分発揮して、適切な待遇において生き生きと就労できるよう、必要な支援等 を講じていく必要がある。 特に、高齢者の体力や身体機能は個人差があり、疾病やけがのリスクだけではなく、若年層 に比べて、転倒や墜落・転落などの労働災害のリスクが高く、休業も長期化しやすいことも知 られている。働く高齢者の特性や業務の内容等の実情に応じた施設・装置の導入や作業内容の見直しなどの配慮により、全ての労働者が働きやすい職場環境づくりにも積極的に取り組むことも重要となる。人生100年とも言われる時代を迎え、雇用・労働の面においても、希望する高齢者が年齢にかかわりなく生き生きと働ける環境の整備が今後も求められるだろう。 エイジフ レンドリー補助金を設けている。また、中小規模事業場に対し、労働災害防止団体が安全衛生に関する 知識・経験豊富な専門職員を派遣し、高年齢労働者対策を含めた安全衛生活動支援を無料で行っている。
■国際化する我が国の労働市場
●OECD諸国では外国人の流入が続いている
OECD諸国がどの国も急速な高齢化に直面している中、多くの国で労働力不足は大きな課題となりつつある。OECD諸国の失業率を長期的にみると、リーマンショックや感染症の拡大による影響で一時的には上昇しているものの、就業率が高い世代が減少していること等を背景に長期的には低下傾向で推移している。失業率の低下は、企業にとっては労働力確保が難しくなっていることを示しており、人手不足が長期的な課題となりつつあることを示している。こうした中で、多くのOECD諸国において外国人の流入が増加している。2013年と2019年における人口に占める外国人の流入率であるが、外国人の流入は多くの国で増加している。我が国で働く外国人の数は、OECD諸国の中では低い水準にあるが、近年大きく増加し、人口に占める割合も上昇している。
(つづく) Y.H