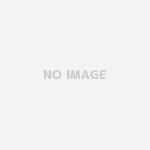キャリコンサルタントとして活躍している方からの投稿をお送りします。
粂井さんの「一方的な力」と「相互的な力」
●相互的という言葉は、物事が互いに影響し合ったり、つながりを持ったりする関係を示す言葉です。特に、ある行為や影響が一方的でなく、双方向の応答がある場合に使われます。たとえば、相互的な関係では「AがBに影響を与え、BがまたAに影響を返す」というように、両者の関わりが強調される力が「相互的な力」のです。
「相互的」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!|コトバスタ
●皆さんは「力」と聞くと、どのようなイメージが浮かびあがるでしょうか。
たとえば、相手に何度もお願いしていることがいつまでたっても出来上がってこないときに、しびれを切らして使うような、強制的な力でしょうか? それとも、リーダーが目標に向かってどんどんチームの生産性を上げて引っ張っていく統率力のようなものでしょうか? 私たちキャリコンサルタントはしばしば、「力」という響きには、ある目標などへ向け、探求や内省などは伴わず、欲するものを手に入れるための一方向的なはたらきかけである、といった印象をもつことがあります。
「力」にもいろいろな種類があります。私たちキャリコンサルタントが普段の会話にて行うひとつひとつの発言に込める力の中にも、一方的に自分の要求を通そうと態度を強めたり、納得させるために自身の論理を展開することもあれば、相手の意見や意図をくみ取るために熱心に耳を傾け、相手から学ぶことによって自分のスタンスをその都度変えていくような、双方向への影響を前提とした発言のスタイルもあります。
組織や社会に変容を起こすことができるリーダーは、「一方的な力」よりも「相互的な力」を用いることが多く、多様な種類の力を状況に応じて組み合わせることに長けている傾向にあります。それでは、この「一方的な力」「相互的な力」には、具体的にはいったいどのような力があり、私たちキャリコンサルタントはどのように使い分けていけばよいでしょうか?
●変容をもたらすリーダーの8つの力
力は主に以下の8つの種類に分けることができます。それぞれにどのような力か、詳しくみていきましょう。
(ビル・トルバート著「行動探究」を参考にチェンジ・エージェントにて改変
まず、一方的な力の代表として、「威圧的な力」「魅了する力」「論理の力」「生産する力」があります。「威圧的な力」とは、自分の勝ちの最大化に向け、物事へ反応をする形で発揮する力です。「魅了する力」とは、自他ともに負の感情を引き起こさないよう、ユーモアやカリスマ性をもって相手や周囲のひとの支援を呼び込む力です。どちらも、状況や出来事に対する反応として、窮地に陥ってしまった際などに、他者よりも自分の利益や保身のために使われがちです。
「論理の力」とは、論理を用い、合理性を最大化しようとする力です。「生産する力」とは、その働きかけにより実際に組織において自分と他者の行動を生み出すような力です。これらの二つはどちらも、自分の定義する軸や戦略、目標に向かって、人を巻き込みながらそれらを実行・実現へ向けて推進していくための力です。物事をより効率的に進めようと努めたり、目標達成のための方針に改善を加えたり、という点では単なる反応ではなく意図的な自己修正の力が備わっていますが、いずれにしても最終的な正解は「自分の中」にあるという点では相互的な影響を前提にしているとはいえません。
●以上の4つの一方的な力に対し、相互的な力とはいったいどのようなものでしょうか。
相互的な力の代表としては、「先見の力」「自己合致の力」「さらけ出す力」「解放的な規律の力」があります。「先見の力」とは、過去、または個々のビジョンに捉われずに将来の新しいビジョンを生み出していく力です。「自己合致の力」とは、理論と実践の間の不一致をみつけ、明確に指摘し、修正し、それによって個人や集団の一貫性、有効性を高めていく力です。自分の中に既に存在する答えを正当化するためにひとを説得したり導いたりするのではなく、常に他者や状況から学びながら、ビジョンや戦略、自身が物事を見るときの前提を新たにしていきます。「さらけ出す力」は、実践的な愛情と探求によって生み出されます。互いに対し用心深く、いまこの瞬間に必要であれば自分自身をいつでもさらけ出し、自分と他者の意図やビジョンを再構築するきっかけをつくりだします。
最後の力は、これまでに出てきたすべての力を折り合わせて用いる力です。「開放的な規律の力」は、個人や集団のパターンを破壊させる客観の構造や状況を適したタイミングで作り出すことにより、個人の発展や組織や社会の成果をもたらします。どちらの力も、組織や集団におけるその場の変容を起こしやすくしようという能動的な意図から生まれます。
●8つの種類の力を見ていくと、どのようなことがわかるでしょうか。キャリコンサルタントとしてどの力を主に用いて普段人と話をしたり、行動をしたりしていますか? つい使ってしまっては望む結果が得られないばかりか、関係性や組織風土を悪化させてしまうような力はないでしょうか? 状況や場面に応じて、より高次の力をおりあわせることで効果は絶大なものとなります。とりわけ、相互的な力は、相手を省みずに自身の望む結果を得るだけでなく、望む結果やそこでの役割について相互互恵的な思考や前提をもてて初めて効果的に活用ができます。
キャリコンサルタントは自分が主に用いている力の特徴に気づき、組織の変容や自己の変容のためにもし必要であれば、ぜひ新しい種類の力も選択肢に入れてみませんか?
つづく Y.K