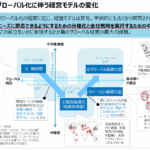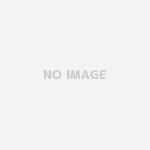韓国の社会保障制度の2回目です。近年、日本の会社は製造業を中心に海外進出を急速に進めています。すでに進出のピークは過ぎていると思われますが、キャリアコンサルタントが海外進出の日本企業で働く人と接触する機会はどんどん増加しています。私は2000年以降5回韓国を訪問していますが、年々産業界の競争力が上がっていることに驚きをもっています。
【生活保障制度】
1999年、従来の生活保護法が廃止され国民基礎生活保障法が制定されたました。国民基礎生活保障の構造は次のようになっています。①生計給付(衣服、食料等日常生活に基本的に必要な費用を支給するもの)
②医療給付(健康的な生活を維持するために医療費を支給するもの)
③住居給付(住居安定に必要な賃借料、修繕費等を支給するもの)
④教育給付(授業料・教材費等の教育費用を支給するもの)
⑤出産給付(出産の際に支給するもの)
⑥葬祭給付(運搬・火葬・埋葬等葬祭措置に必要な費用を支給するもの)
⑦自活給付(自活に必要な費用の支給、技能習得、就職あっせんや勤労機会を提供するもの)国民生活は、これら7つの給付の支給を通じて最低レベルが保障されます。しかし、この制度は貧困層のセーフティネットとしての機能を果たす一方、非受給貧困層等の福祉問題、低い保証水準及び就労への誘引の欠如等の限界が指摘されてきました。この実情を踏まえ、「第1次基礎生活保障総合計画」(2018~2020)が策定され、非受給貧困層の減少を図るため扶養義務者基準の段階的廃止、国家が国民に対して保障すべき必要最低限の生活水準(ナショナルミニマム)に基づく各種給付の拡大・見直し、勤労能力がある受給者の自立基盤作りのための自活勤労事業の拡大と自活給付の段階的引上げ等が盛り込まれていきました。その後、「第2次基礎生活保障総合計画」(2021~2023)が策定され、貧困地帯の解消、保障水準の強化、脱貧困支援等を主要課題として、基礎生活保障制度の対象者と保障水準は持続的に拡大してきました。
(出典)厚生労働省 001105071.pdf (mhlw.go.jp)
■社会サービス
(1)少子高齢化の現状と対策韓国の合計特殊出生率は、OECD加盟国中最下位水準にある。1970年の統計開始以来、出生率は下落し、2005年に最低値の1.08を記録。2006~2017年は1.05~1.30を推移していたが、2018年には0.98と1を下回り、2021年には0.81と出生統計開始(1970年)以来の低水準を記録した。一方、65歳以上の高齢者人口は、2000年に約339万人となり、総人口の7.2%を占めて高齢化社会に突入した。2020年の高齢者人口は総人口の15.7%(約815万人)となっており、今後も増加を続け、2025年には20.3%に達して超高齢社会に突入することが見込まれている。他の先進国に比べて高齢化へのスピードが速いのが特徴的である。このような少子高齢化問題に全政府的に対応するため、2005年9月に「低出産・高齢社会基本法」に基づき、関連省庁と民間専門家等が参加する「低出産・高齢社会委員会」を設置。同委員会を中心に国の少子高齢化対策の基本となる「低出産・高齢社会基本計画」を策定し5年ごとに目標設定・見直しを行っている。2020年には、「第四次低出産・高齢社会基本計画(2021~2025)」を策定した。主な内容として、少子化対策関連では、0~1歳の乳児手当の新設、育児休業所得代替率の引上げ、多子世帯への授業料支援等、高齢社会対策関連では、継続雇用支援、基礎年金拡大等、多層所得保障体系の強化等を段階的に実施することとしている。
(2)高齢者保健福祉政策
韓国政府はこれまで、国民年金の改善、基礎老齢年金や高齢者長期療養保険制度の導入、高齢者雇用の拡大、独り暮らしの高齢者等の安全と保護の強化、認知症対策の推進などの基本的な政策の枠組みを継続的に整備してきた。
イ 高齢者の介護総合サービスの提供
高齢者の介護総合サービスは、独力では日常生活を営むことが難しい高齢者に、家事・活動支援又はケアサービスを提供するために2007年から実施されている。満65歳以上の高齢者で世帯所得と健康状態を考慮した結果、ケアサービスが必要と判断された者に対して訪問サービス、デイサービス、短期家事サービスが提供される。訪問サービスは月27時間又は36時間の単位で、利用者の居宅に高齢者介護の資格所持者が訪問する方式で、食事・入浴等の介護や、掃除・洗濯等の家事支援が行われる。デイサービスは月9日又は12日の単位で、施設までの送迎サービス付きで、施設において機能回復のための活動や食事が提供され、短期家事サービスは1か月24時間又は2か月48時間の単位で、家事支援が提供される。なお、費用は、所得水準と利用時間に応じた本人負担金と地方自治体の支援金で賄われている。
■認知症施策の推進
2022年現在、65歳以上の高齢者人口の約10.3%を占める約88万人程度が認知症であると推定され、この割合は今後も増加する予測である。このような状況下、認知症高齢者本人のみならず、その家族へも精神的、肉体的、経済的に深刻な負担をもたらし生活の質の低下や医療費負担の増加が課題となっている。韓国の認知症対策は、2011年に「認知症管理法」が施行されたことから本格的に始まった。国内に中央及び広域認知症センター(2012〜2016年)等が設置された。更に2017年には、認知症高齢者とその家族の負担を国が責任を持って軽減する「認知症国家責任推進計画」を発表した。以降、本人とその家族が医療・介護を連携させた一連のサービスが受けられる「認知症安心センター」の拡充、重度認知症患者の健康保険自己負担率の大幅な引き下げ(最大60%から10%)、軽度認知症患者への長期療養保険の等級付与による長期療養サービスの適用等を推進している。2008年に初めて樹立された「国家認知症管理総合計画」も、引き続き2020年には第4次計画(2021~2025)が樹立されており、中央・圏域・地域単位で体系的な認知症管理政策が推進されている。
■保育政策
(1)乳幼児の保育政策
保育支援の拡大や保育施設等のインフラ拡充など、保育政策は女性の経済活動増加と超少子化現象に対応するための重要な政策の一つとなっています。2018年から、「第三次中長期保育基本計画(2018〜2022)」が進められています。
①保育の公共性強化
②保育システムの改編
③保育サービスの質の向上
④親への子育て支援拡大
国公立保育所に対する量的な需要が高く、質的には保育所の十分な利用時間の保障と良質な保育サービスに対する要求が高まっています。2023年には第4次中長期保育基本計画が樹立され、今後5年間の保育政策ロードマップが提示される予定となっています。
(イ)国公立保育所の拡充
2019年には、654か所の国公立保育所を新規に設置することで2021年時点で施設数は合計5,437か所となりました。保育の公共性強化のために国公立保育所を持続的に拡充してきましたが、なお、国公立保育所の早期拡充を目的として、民間・家庭保育所の長期賃借、既存の保育所の買入れ、共同住宅管理棟の保育所リモデリング等が実施し、2022年には「公共保育利用率」40%の達成を目標としています。
(ロ)保育料の支給
2009年より、補助金形式で保育所に直接支給していた政府支援の保育料を、親に直接支給する形に変更し、保育電子バウチャー「子ども幸福カード」を発給するようになりました。2013年からは、保育所を利用する0~5歳児を扶養するすべての所得階層に対し年齢別に定められた保育料を利用者に支給するとともに、保育所等を利用しない0~5歳児に対しては養育手当を支給しています。保育所と地方自治体の事務負担を減らす等の観点から、親は、電子決済により保育料(政府支援金+家庭の負担金)を納付する制度となっています。2021年からは、妊娠・出産時に発行される「国民幸福カード」と統合され、妊娠・出産時に健康保険で支援される診療費のバウチャーと保育料等のバウチャーが一括で利用できるようになりました。
(ハ)保育士の処遇改善
保育士の処遇改善のために乳児クラスの担任保育士には月3万円の勤務環境改善費を、担任を兼職する院長には月1万円の手当てを、3~5歳の共通教育課程であるヌリ過程の担任教師には月4万円のヌリ過程担任手当を支給しています。また、、保育士の勤務条件改善を図る目的で、保育士の休暇等による保育サービス空白解消のための代替教師(2021年時点で4,100人)の派遣をしています。
■児童福祉政策
1961年、児童福祉政策の推進基盤となる「児童福祉法」が制定されました。幾度かの改正を経て現行では児童の人権を保護し、児童の利益を優先する支援を目指しています。2015年より、本法律に基づき関係省庁合同で5年毎に「児童政策基本計画」を策定していますが、「第2次児童政策基本計画(2020〜2024)」では、「児童が幸せな国」をビジョンとして設定し、その実現のために「子どもの権利の尊重と実現」、「子どもが現在の幸せを享受できる環境づくり」を政策目標としています。
(イ)児童手当の導入
2018年、「児童手当法」を制定・導入し児童の養育への国の責任を強化しました。所得下位90%の世帯の満6歳未満(0〜5歳、生後72か月まで)の児童225万人に月額1万円の児童手当を支給しました。2022年には、経済的水準の撤廃や対象者年齢の引上げを行い、273万人に児童手当を支給しています。
(ロ)児童福祉施設等
児童が生活する児童福祉施設や児童に家庭と同じ住居条件と保護を提供するグループホームにおける児童の保護、児童を一時的に家庭で保護する家庭委託等を実施し、両親による養育が困難な要保護児童を健全な社会人に育成するための施策を実行しています。
(ハ)児童虐待防止対策
2020年、「包容国家児童政策」を「児童福祉法」に改正して、全地方自治体に児童虐待専門担当公務員を配置しました。児童の保護のために、被害児童に対する応急措置後の保護空白等が発生する場合に、自治体の保護措置決定があるまで被害児童を分離して一時保護する「即時分離制度」を導入しています。
(以上)
平林良人