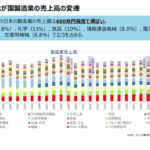キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。
前回に続き、経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」から「製造業企業の状況2では、財務指標から見た企業の収益性・効率性・健全性が中心に扱われています。図表を補完しながらより踏み込んだ解説をします。

(出典)経産省 製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性2024年5月製造産業局製造業企業の状況 – 検索
◆「製造企業の状況」解説
――ROE・純利益率・資産効率から読み解く、“縮小均衡”に陥る日本の製造業
はじめに:このページが明らかにしていること
このページは、日本の製造企業が売上や利益を拡大しているように見えても、経営の質の面では米欧に比べて大きな課題を抱えているという構造的問題に焦点を当てている。とくに、
① 純利益率(どれだけ効率的に利益を出しているか)
② ROE(自己資本利益率)(株主資本に対する収益性)
③ 総資産回転率(資産の運用効率)
④ レバレッジ比率(財務の安全性と積極性)
といった財務指標を用いながら、日本企業が長年「守りの経営」にとどまり、成長投資に踏み出せない“縮小均衡”に陥っている懸念を丁寧に提示している。
1.純利益率は上昇傾向——だが米欧との格差は依然大きい
スライドには、日本・米国・欧州の**製造業の純利益率(Net Profit Margin)**の推移が示されている。ここでは、以下のポイントが重要である:
●日本企業の純利益率は、2000年代以降着実に上昇傾向にある
→ 売上が横ばいの中で利益を増やしているという点では“効率的”に見える
●しかし、その水準は米国・欧州の製造業よりも依然として2〜3ポイント程度低い
→ 利益率の絶対値で比較すれば、競争力はまだ見劣りする
この背景には、日本企業がコスト削減を進めて利益を捻出してきた一方で、製品価格や付加価値の高さで収益を上げる力(=価格交渉力)が弱いという構造的な課題がある。
2.ROE(日米欧比較):レバレッジ低下で資本効率に劣位
ROE(Return on Equity)は、企業が株主資本をどれだけ効率的に運用して利益を上げているかを示す重要な指標である。このスライドでは、日本企業のROEが次のように評価されている:
●日本企業のROEは米欧より5~10%程度低い水準で推移
●特に2010年代以降は、米国企業が20%台、欧州企業も15%前後を記録する中で、
日本企業は10%未満にとどまる年が多い
その原因として挙げられているのが、「レバレッジ比率の低下」である。
イ なぜレバレッジが下がるとROEも下がるのか?
●レバレッジ(自己資本比率の逆数)は、“他人資本(借入)を使って自己資本の利益を拡
大する力”
●日本企業は1990年代のバブル崩壊後、過剰債務を解消し、借入体質から自己資本体質へと移行
その結果、財務は健全化したが、資本を活かしてリスクを取りに行く姿勢が弱まった
→ 利益が出ても、資本に対する“収益性”は伸び悩む
つまり、ROEの低さは、“慎重すぎる財務戦略”の裏返しでもある。
●総資産回転率:投資控えが“効率の低下”をもたらす
次に取り上げられているのが、**総資産回転率(売上高 ÷ 総資産)**である。これは、企業がどれだけ効率的に資産を運用して売上を上げているかを測る指標である。
① 総資産回転率は日米欧ともに長期的に低下傾向
→ これは世界的な構造変化であり、単に日本固有の問題ではない
② しかし、問題は日本企業の「収益性の低さ」と組み合わさると、効率性そのものが疑われること
たとえば、総資産回転率が低下しているのに、高利益率が維持されているのであれば、資産の質は高いと評価できる。しかし日本の場合は、
●売上横ばい+利益率は米欧より低い+資産も遊休化が多い
● ⇒ 「資産は守っているが、活用できていない」という見方も可能
その背景には、**過剰な設備投資の抑制(ディスインベストメント)がある。つまり、投資を絞りすぎて資産の質が高まらず、結果的に“資産効率が悪化”**している構図である。
●「縮小均衡」という構造:守りの経営が生んだ静かな停滞
このページ全体を貫いているキーワードが、「縮小均衡(defensive equilibrium)」である。
これは、次のような現象を指す:
| 指標 | 状況 | 含意 |
| 売上高 | 横ばい~微減 | 市場拡大が期待できず、外需依存も限界 |
| 利益率 | 改善傾向 | コスト削減や構造改革で“利益は出せている” |
| ROE | 低水準 | リスクを取らず、利益も資本も活かせていない |
| 総資産効率 | 低下 | 資産運用が保守的で、投資循環が弱い |
このページ全体を貫いているキーワードが、「縮小均衡(defensive equilibrium)」である。
これは、次のような現象を指す:
●政策的含意:企業が「稼ぐ力」を活かす仕組みを再設計せよ
このような構造に対して、政策的には次のような対応が必要である:
イ “攻めの投資”を後押しする環境整備
●グリーン投資減税、DX補助金、研究開発税制の拡充
② 金融機関との協調によるリスクマネー供給体制の再構築
ロ 企業のROE向上を促す制度的な圧力
●東証による「資本コストと株価を意識した経営」要請(PBR1倍割れ対策)
●コーポレートガバナンス改革による経営陣の意識変革
ハ 中長期視点の経営指標重視への転換
① 単年度の利益だけでなく、「5年後の収益力」や「人的資本投資」を重視
② サステナビリティ経営(非財務指標)の導入・評価
総括: 「利益は出ている」の先へ――“再投資による成長の回路”を取り戻せ
日本の製造業は、数値上では純利益を上げ、企業体質も改善してきた。だが、ROEや資産効率の観点では、依然として米欧に大きく後れを取っている。その背景には、財務の安全性を追い求めすぎて、投資や成長を抑制してきた企業行動がある。
今求められているのは、内部留保を「守りの蓄積」から「攻めの再投資」へ転換する企業変革である。利益を「次の成長の源泉」へとつなげるための制度設計と経営マインドの改革が、いままさに問われている。
このページは、静かに、だが厳しく、日本の製造業の“内なる停滞”を映し出しているものであるといえる。
(つづく) Y.H