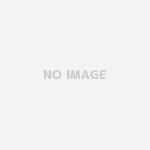キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
前回に続き、経済の社会の構築について、お話しします。今後の日本経済は、より高い製品開発能力を獲得し、製品の付加価値を高めながらアジアを中心とする諸外国との経済分業の下で、互恵的な経済社会の発展を追及していくことが基本的な方向です。
■国際海上貨物輸送ネットワークの機能強化
経済のグローバル化が進展する中、世界的な海上輸送量は年々増加してきており、大量一括輸送による海上輸送の効率化の観点から、コンテナ及びバルク貨物輸送船舶の大型化等が進展 しています。 コンテナ貨物については、日本の港湾は、釜山港や上海港といったアジア主要港に比較して相対的に貨物量が少ないこと等により、船舶の大型化が進む、北米・欧州等と日本とを結ぶ国際基幹航路の寄港数が減少傾向にあります。さらに、新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、北米西岸を中心とする港湾混雑等により船舶の運航スケジュールに乱れが生じ、外航コン テナ船社による、運航スケジュールの正常化に向けた更なる寄港地の絞り込みが行われた結果、国際基幹航路の日本への寄港数が減少して います。 また、バルク貨物については大型船への対応が遅れており、相対的に不利な事業環境による国内立地産業の競争力低下等が懸念されています。 このような状況を踏まえ、サプライチェーンの安定化等に向けて、国際基幹航路の維持・拡大に、より一層取り組む必要があるほか、主要な資源・エネルギー等の輸入の効率化・安定化に向けた取組みを行っています。また、このような取組みとともに、引き続き、国際・国内一体となった効率的な海上輸送ネットワークを実現するための取組みを推進するとともに、施策の更なる充実・深化を図ることとしています。
○国際コンテナ戦略港湾の機能強化
国際基幹航路の我が国への寄港を維持・拡大することにより、企業の立地環境を向上させ、 我が国経済・産業の国際競争力を強化するため、国際コンテナ戦略港湾である京浜港・阪神 港に、国内外から貨物を集約する「集貨」、港 湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コ ンテナターミナル等の整備の推進等によるコス トや利便性の面での「競争力強化」の3本柱の施策に加え、世界に選ばれる港湾の形成を目指し、港湾の脱炭素化や港湾におけるデジタル・ トランスフォーメーション等の取組みを進めている。
「集貨」については、既存ストックを最大限に活用しつつ、集貨を促進するため、国際コンテナ戦略港湾における実証事業を通じて、複数のターミナル間における国際基幹航路と国内 のフィーダー輸送網等との円滑な接続・積み替 え等に関する課題を検証し、ターミナルの一体 利用に向けた機能強化を推進している。
「創貨」については、多様な物流ニーズに対応するロジスティクス・ハブを形成し、新たな貨物需要を創出するため、流通加工機能を有す る物流施設のコンテナターミナル近傍への立地 の促進を図った。「競争力強化」については、国際基幹航路に就航する大型船の入港を可能とするため、国際コンテナ戦略港湾において、国際標準の水深、広さを有するコンテナターミナル等の整備を推進した。さらに、「ヒトを支援するAIターミナル」の 実現に向けた取組みを深化させて、コンテナターミナルの更なる生産性向上や労働環境改善 に資する技術開発を推進するため、技術開発 テーマを国において設定し、具体の技術開発案件の実施を支援している。また、情報通信技術を活用し、ゲート処理の迅速化を図るために開発した新・港湾情報システム「CONPAS」の導入促進に向けた取組みを推進するとともに、ターミナルゲート作業を迅速化・効率化するための高機能なゲートの導入を支援する。
加えて、港湾を取り巻く様々な情報を電子化 し、生産性向上を図る「サイバーポート」については、港湾管理分野(港湾行政手続等)の運用を令和6年1月より順次開始、港湾物流分野 (民間事業者間の港湾物流手続)は商流・金流 分野のプラットフォームとの連携等、港湾インフラ分野(港湾施設情報)は令和6年度中に全 932港への拡大を行い、3分野一体での利活用 を推進する。 (出典)国土交通省 令和6年版 国土交通白書
○資源・エネルギー等の安定的かつ効率的な海上輸送ネットワークの形成
産業や国民生活に不可欠な資源・エネ ルギー・食糧の安定的かつ安価な輸入を実現するため、企業間連携による大型船を活用した共 同輸送に対応可能となるよう、徳山下松港、水島港、志布志港において岸壁等の整備を進めています。
■国際競争力の強化に向けた航空物流機能の高度化
国際航空貨物輸送については、今後も伸びが期待されるアジア発着貨物を積極的に 取り込むため、首都圏空港の機能強化や関西国 際空港の貨物ハブ化の推進、中部国際空港の利活用の促進に向けた取組み等を進めています。
■我が国物流システムの海外展開の推進
サプライチェーンのグローバル化が深化する中、我が国の産業の国際競争力を維持・向上さ せていくためには、質の高い国際物流システム の構築が求められている。しかし、我が国の物流システムのアジア地域への展開に当たっては、相手国の制度上・慣習上等の課題が存在している。 このため、物流パイロット事業、政府間での政策対話、㈱海外交通・都市開発事業支援機構 (JOIN)による物流関連インフラ整備への資金支、人材育成事業、物流システムの国際標準化の推進等を通じ、官民連携により物流システ ムの海外展開に向けた環境整備を図っている。(出典)国土交通省 令和6年版 国土交通白書
■国際物流機能強化に資するそのほかの施策
大都市圏における国際物流の結節地域である 国際港湾等周辺及び物流・産業の拠点である港湾において、物流拠点及び物流施設の整備・再整備を推進することにより、大規模災害時における防災機能の向上を図りつつ、都市環境の改善と併せた国際競争力の強化及び効率的な物流網の形成を図る必要があります。 国際物流については、ウクライナ情勢の影響 や海外港湾の混雑等の様々なサプライチェーン の途絶リスクを踏まえ、我が国企業にとって代替的な輸送オプションを確保し、強靱なサプラ イチェーンの構築を図るため、従来の輸送手段・ルートを代替又は補完する輸送手段・ルー トについて実態調査や実証輸送を実施しています。
◆産業の活性化
■鉄道関連産業の動向と施策
●鉄道事業の概況
1980年代後半にかけて、鉄道の旅客輸送量は大きく伸び、近年は人ベース、人キロベース ともに緩やかな増加傾向にあったが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響により、減少しています。令和3年度の鉄道の旅客輸送量は、人ベース では対元年度比約25%減の約188億人、人キロベースでは対元年度比約33%減の約2,901億人キロとなっています。全国に218社ある事業者をカテゴリ別に分けて旅客輸送量を見る と、人ベースでは、都市部に通勤路線等を多く持つ大手民鉄(16社)やJR(6社)がそれぞ れ約4割前後で多く、次に地方交通(175社)、 都市部で地下鉄や路面電車を運営する公営(11 社)であす。一方、人キロベースでは、新幹線をはじめ幹線輸送網を有するJRが5割を超え、大手民鉄の約1.8倍以上となっています。
●鉄道事業
○鉄道分野の事業基盤強化に向けた取組み
人材不足に対応し、特に経営の厳しい地方鉄道におけるコスト削減等を図るため、踏切があるなどの一般的な路線での自動運転の導入促進に向けた要素技術の開発、無線通信技術の活用により信号機等の地上設備の削減を可能とします。 地方鉄道向けの無線式列車制御システムの開発、鉄道車両における屋根上検査業務の効率化に向けた画像解析手法の開発等、鉄道分野における生産性向上に資する取組みを推進します。 また、担い手確保のため、鉄道運賃に係る収入原価算定要領を見直し、適正な賃金上昇を反映できるよう人件費の算定方法等の見直しを行いました。さらに、特定技能制度の活用による外国人材の受入れ、動力車操縦者試験の受験資格の見直し(年齢要件の引下げ)等の取組みを進めています。
○JRの完全民営化に向けた取組み
かつての国鉄は、公社制度の下、全国一元的 な組織であったため、適切な経営管理や地域の実情に即した運営がなされなかったこと等から、巨額の長期債務を抱え経営が破綻した。このため、昭和62年4月に国鉄を分割民営化し、鉄道事業の再生が行われたところである。 令和5年4月には、JR各社の発足から36年を迎えた。国鉄の分割民営化によって、効率的 で責任のある経営ができる体制が整えられた結果、全体として鉄道サービスの信頼性や快適性が格段に向上し、経営面でも、JR東日本、JR 西日本及びJR東海に続いてJR九州も完全民営化されるなど、国鉄改革の所期の目的を果たしつつある。一方で、JR北海道、JR四国及びJR貨物については、未だ上場が可能となるような安定的利益を計上できる段階には至っていない ため、国としても、設備投資に対する助成や無利子貸付け等、経営自立に向けた様々な支援を 行ってきた。しかしながら、JR北海道及びJR 四国については、地域の人口減少や他の交通手段の発達、低金利による経営安定基金の運用益 の低下等に加え、新型コロナウイルスの感染拡大の影響やその後の利用者の行動変容により、その経営環境はより一層厳しさを増している。 また、JR貨物については、近年は経常黒字を計上している年度もあるものの、災害等の影響を受けやすいなど安定的な事業運営にはなお課題が残されている。 こうした背景を踏まえ、令和3年度以降も各 社の経営状況に応じた適切な支援を講じ、各社 の完全民営化に向けた経営自立を図っていくこ とを目的に、3年3月に「日本国有鉄道清算事 業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改 正する法律」(令和3年法律第17号)が可決・ 成立し、各社への支援の期限が延長された。これに基づき、3年度より、各社に対して経営安 定基金の下支え、安全に資する設備投資や修繕費に対する助成金の交付、省力化・省人化に資 する設備投資のための出資、DES(債務の株式化)等、経営自立に向けた支援を順次実施している。
(出典)国土交通省 令和6年版 国土交通白書
(つづく)Y.H