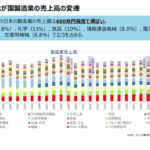キャリアコンサルタントが知っていると有益な情報をお伝えします。
ICTとは、情報通信技術を意味します。ICTの普及により、私たちの生活は各段に便利になりました。インターネットを使えば、世界中の情報をリアルタイムで簡単に手に入れることができますし、スマホを片手に家族や友達と手軽に連絡したり、音楽や映画を楽しむこともできます。このように、ICTは私たちの暮らしに溶け込み、より快適な楽しいいために欠かせないツールとなっています。今回は、ICT活用についてお話します。
◆教育の情報化
■学習指導要領の改訂と情報活用能力
平成29年3月に小学校及び中学校の学習指導要領を、30年3月に高等学校の学習指導要領を公示しました。こ の改訂により、「情報活用能力」を、言語能力などと同様 に「学習の基盤となる資質・能力」と位置づけ、各学校におけるカリキュラム・マネジメントを通じて、教育課程全体で育成するものとしました。前述の学習指導要領総則では、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどのICT環境を整備し、これらを適切に活用した学習活動の充実に配慮することを新たに明記するとともに、小学校学習指導要領では、コンピュータでの文字入力など 情報手段の基本的な操作を習得する学習活動を充実するこ とについて明記しています。加えて、小学校段階でのプログラミング教育を必修化するなど、小・中・高等学校を通 じてプログラミングに関する内容も充実しています。 文部科学省では、これらの学習指導要領の下で、教育の情報化が一層進展するよう、教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組の参考にしてもらうため、 「教育の情報化に関する手引」を作成・公表しています。
●情報活用能力の育成
情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて 情報の収集・整理・比較・発信・共有等を行うことができる力であり、さらに情報手段の基本的な操作の習得や、プ ログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等も含むものです。これを確実に育んでいくためには、各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要です。 前述のとおり、情報活用能力はカリキュラム・マネジメ ントにより教育課程全体で育成することが必要であり、各 学校は、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、情報活用能力育成の観点から教育課程を編成して、組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図ることが求められます。文部科学省では、情報活用能力を体系的に整理し、情報活用能力の育成事例やカリキュラム・マネジメントモデルに基づく取組を整理、公表しています。さらに、令和3年度に児童生徒の情報活用能力の定量的測定のための調査を実施し、分析結果及び一部の問題を公表しています。また、6年度には、再度調査を実施することとし、各教科において求められる具体的な能力・目安やその育成に必要な 指導例等、児童生徒に身に付けさせるべき情報活用能力を提示するための準備をしています。 (出典)文部科学省 令和5年版 文部科学
●プログラミング教育の実施に向けた取組
小学校においては、学習指導要領で、プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施することを明記し、算数、理科、総合的な学習の時間において、プログラミングを行う学習場面を例示してい ます。小学校段階で体験的にプログラミングに取り組む狙いは、プログラミング言語を覚えたり、プログラミングの技能を習得したりといったことではなく、論理的思考力を育む活用とともに、プログラムの働きやすさ、情報社会がコンピュー タをはじめとする情報技術によって支えられていることなどに気付き、身近な問題の解決に主体的に取り組む態度やコ ンピュータ等を上手に活用してよりよい社会を築いていこう とする態度等を育むこと、さらに、教科等で学ぶ知識及び技能等をより確実に身に付けさせることにあります。 また、プログラミングに関する内容が既に必修となって いる中学校技術・家庭科(技術分野)において内容の充実 を図るとともに、高等学校においては、共通必履修科目と して「情報Ⅰ」を設定し、全ての生徒がプログラミングのほか、ネットワーク(情報セキュリティを含む)やデータ ベースの基礎等について学ぶなど、小・中・高等学校の全ての学校段階を通じてプログラミング教育を実施すること としています。 文部科学省では、小学校プログラミング教育について は、学習指導要領や同解説で示している基本的な考え方等 を分かりやすく解説した「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」*3を公表するとともに、文部科学省、総務省、経済産業省が連携して、民間企業・団体等とともに平 成29年3月に「未来の学びコンソーシアム」を設立し、現在はポータルサイトにおいて、民間企業・団体等による 取組等の紹介を通じて、着実な実施に向けた支援を行って います。また、中学校・高等学校においては、「中学校技術・家庭科(技術分野)のプログラミングに関する実践事 例集」や「高等学校情報科に関する特設ページ」(情報Ⅰ の授業動画等)の作成・公開を行っています。文部科学省においては、引き続き、小・中・高等学校を通じたプロ グラミング教育の円滑な実施のため、実践事例等の有益な情報提供等を行うこととしています。
●学校のICT環境整備
令和元年度及び2年度補正予算において 「GIGAスクール構想の実現」として合計4,819億円を計 上し、義務教育段階における1人1台端末の整備や、学校 における高速大容量のネットワーク環境の整備を行うとともに、3年度補正予算において、指導者用端末の確保や大型提示装置の整備など、ICTを活用した授業を高度化するために必要となる機器の追加整備の支援を実施しました。 こうして整備した1人1台端末も利活用が進むにつれて、故障端末の増加や、バッテリーの耐用年数が迫っているところ、GIGAスクール構想第2期を念頭に、今後5年 程度をかけて端末を更新するとともに、端末の故障時等に おいても子供たちの学びを止めない観点から、予備機の整 備も進めることとし、令和5年度補正予算において、当面 7年度までの整備に要する経費として2,643億円を計上し ました。今後の更新に当たっては、都道府県に基金を造成 し、都道府県を中心とした共同調達を進めるなど、計画 的・効率的な端末整備を推進していきます。 また、学校ICT運用を広域的かつ組織的に支援する 「GIGAスクール運営支援センター」については、端末活 用の日常化を一層進めるため、自治体の状況に応じたメ ニューなど、機能強化のための予算を令和6年度予算にお いても計上しています。 また、高等学校においては、令和4年度から新学習指導 要領が実施され、「情報Ⅰ」の実施や、情報活用能力を学 習の基盤となる資質・能力の一つとして育成していくこと が必要とされたことを踏まえ、各自治体において、設置者 負担や、保護者負担による1人1台端末の整備が進められているところです。 なお、「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(平 成30年から令和4年)」については、計画期間を2年間延長し、令和6年度までとしていますが、7年度以降の新たな学校のICT環境整備の在り方について、中央教育審議会にワーキンググループが設置され、議論が進められてい るところです。 教員のICT活用指導力の向上については、文部科学省 において、教科等の指導におけるICTの活用について記 載した「教育の情報化に関する手引」を作成・公表すると ともに、教職員支援機構において「学校教育の情報化指導 者養成研修」を実施しているところです。また、各教科等 のICTの効果的な実践事例等の作成・周知や、「学校DX 戦略アドバイザー」による専門的な助言や研修支援の実施 等の取組を進めています。 さらに、令和3年度から引き続き、日々子供たちと向き合う教師の方々や教育委員会等の学校設置者に対する継続 的な支援を充実するため、教育委員会や学校現場から迎え 入れた教師の方々で構成された「GIGA StuDX(ギガ ス タディーエックス)推進チーム」が専属で指導面での支援 活動に当たっています。 これらの取組をはじめ、現場の状況を踏まえた取組を進めることにより、今後は、整備した環境を実際に活用につ なげていき、ICT活用を通じて個別最適な学びと協働的 な学びの一体的な充実を図る取組を進めていくことを目指しています。
(出典)文部科学省 令和5年版 文部科学
●遠隔教育の推進
文部科学省では、令和2年度に「遠隔教育システムの効果的な活用に関する実証」を行い、「多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育」、「教科等の学びを深める遠隔教育」、「個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育」、「家庭学習を支援する遠隔・オンライン学習」、「遠隔教員研修」をテーマとした実証事業に取り組み、遠隔教育システ ムの効果的な活用方法に関するノウハウの収集・整理とその効果及び情報通信技術等に関する検証を行いました。 また、令和元年8月より、中学校等において、一定の基準を満たしていると文部科学大臣が認める場合、受信側教員が相当免許状を有していない状況でも、遠隔授業を行うことを可能としました(遠隔教育特例校制度)。その後、都道府県教育委員会等の適切な関工夫が発揮され、より効果的かつ柔軟な実施が可能となる よう、6年3月に、大臣による指定を不要とすること等を 内容とする制度改正を行いました。高等学校については、 平成27年4月より、全日制・定時制課程における遠隔授 業を正規の授業として制度化し、対面により行う授業と同 等の教育効果を有するとき、受信側に当該教科の免許状を 持った教員がいなくても、同時双方向型の遠隔授業を行うことができることとしています。令和3年2月には、高等学校段階における遠隔授業の一層の推進を図る観点から、高等学校等におけるメディアを利用して行う授業の実施に係る留意事項を改正し、遠隔授業を活用して修得する単位 のうち、主として対面により授業を実施するものは、36 単位までとされる単位数の算定に含める必要はないことと しました。また、6年2月にも同留意事項を改正し、受信 側教室等の教員配置や対面により行う授業の時間数等の弾力化を行いました。
(つづく)Y.H