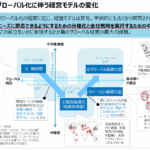キャリアコンサルタントの方に有用な情報をお伝えします。
経済産業省製造産業局が2024年5月に公表した資料「製造業を巡る現状と課題 今後の政策の方向性」からスライド16ページ「日本的経営とワールドクラスのギャップ②」について、図表の内容をもとに文章形式で体系的かつ詳細に解説をします。

(出典)経済産業省 016_04_00.pdf
◆ 「日本的経営とワールドクラスのギャップ②」詳細解説
このスライドは、日本企業がグローバル競争の中で直面する組織運営・意思決定・価値観といったマネジメントシステムと組織文化の課題を、ワールドクラス企業の実態と比較して明示しています。特に、「オフィサーの役割」「意思決定の仕組み」「コミュニケーションの様式」「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の運用」など、企業の中核を成す“ソフト面”の構造に焦点が当てられています。
以下、それぞれの観点について解説します。
①【オフィサーの本分】― 経営と執行の分離が曖昧な日本的役割
日本企業では、執行役員やCxO(チーフ・◯◯・オフィサー)といった経営幹部が、しばしば経営と執行の両方を兼任しているケースが一般的です。その結果、オフィサーが実行業務に追われ、本来担うべき戦略的・未来志向的な職務に十分な時間を割けていないという実態があります。
また、役職名だけが欧米流(例:チーフ○○オフィサー)になっていても、実際には権限が曖昧で、本社内や国内子会社の調整に終始し、グローバル視点での意思決定が弱いという問題が存在します。
対照的に、米国などのワールドクラス企業では、CxOは経営戦略に専念するために組織設計がなされており、執行業務はライン担当役員や事業部長などに委譲されています。また、グローバル組織全体の資源配分や中長期戦略を担うファンクションとして、明確に役割と期待値が設定されています。
②【意思決定スタイル】― 多数調整型のボトムアップ志向
日本の意思決定プロセスは、「根回し」や「合意形成」を重視するボトムアップ型の意思決定が中心です。これは「多数関係者の納得」を優先する文化から来ており、結果として迅速な意思決定が困難となり、競争環境において後れを取る要因となっています。
また、特に不確実性の高い状況や危機時においては、誰もが意思決定を避け、問題を先送りする「様子見」の組織行動が強くなる傾向があります。
これに対してワールドクラスの企業では、トップダウンによる迅速な判断と実行が基本であり、リーダーの裁量と責任が明確です。意思決定に関わる情報やリスク分析は専門部門が支援し、意思決定者はそれに基づいてスピーディに方向を示すことが求められます。
この差異は、単なる風土の違いというよりも、組織設計上の責任構造と権限移譲の制度的不備に起因しており、日本企業が改革すべき深層課題のひとつです。
③【コミュニケーションスタイル】― あうんの呼吸・ハイコンテクスト文化
日本のビジネスコミュニケーションは、言語的な明示よりも、文脈・空気・暗黙の了解に依存するハイコンテクスト型です。これは、日本人同士の共通文化的背景が前提にあるからこそ機能するものであり、多国籍なチームでは極めて非効率・不透明なスタイルになりがちです。
このため、海外では情報共有が滞り、誤解や齟齬を招くこともあります。また、定型報告・形式主義が重視され、本質的な議論や建設的な対話が生まれにくいという構造的欠陥があります。
対照的にワールドクラスの企業では、バックグラウンドの異なる多様な人材が協働することを前提に、ロジカルで明示的なコミュニケーションが重視されます。例えば、議論のプロセスと結論が明文化され、情報共有はシステム上で即時に行われる設計となっており、これが意思決定のスピードと正確性を高めています。
④【MVVの実践】― “掲げる”だけで“根づかない”日本のMVV
MVVとは、Mission(使命)、Vision(将来像)、Value(価値観)の略で、企業の存在意義と行動規範を示す指針です。日本企業でもMVVを掲げる企業は増えていますが、その多くは年頭挨拶や社内報といった一時的・形式的なイベントでしか語られないケースが目立ちます。
そのため、MVVが社員の行動や意思決定と結びつかず、現場にとっては「実感なき言葉」として機能不全に陥っています。特に若手社員にとっては、理念と日常の業務が乖離していることで、企業への共感やエンゲージメントを感じにくくなっています。
これに対して、ワールドクラスの企業では、MVVは単なるスローガンではなく、採用・評価・教育・配置など、すべての人材マネジメントプロセスに組み込まれているのが特徴です。また、MVVを経営戦略の中核として位置づけ、実際の意思決定やプロジェクト遂行において明確に活用しています。こうした徹底した理念経営によって、多様な人材が価値観を共有し、方向性をそろえて動く組織力が実現されています。
総括:組織・人材・価値観のギャップは構造的問題
このスライドで示されているのは、単に「文化の違い」ではなく、経営の構造・制度設計・役割分担・情報の扱い方において、日本企業がグローバル標準から大きく遅れているという現実です。
特に、
〇トップの意思決定スピードと責任の明確さ
〇現場の裁量と判断力を支える仕組み
〇多様性を前提としたコミュニケーションと組織運営
〇MVVを行動規範として「生きた理念」にする工夫
といった観点で、日本企業が変革に取り組む必要性が強調されています。
(つづく)Y.H